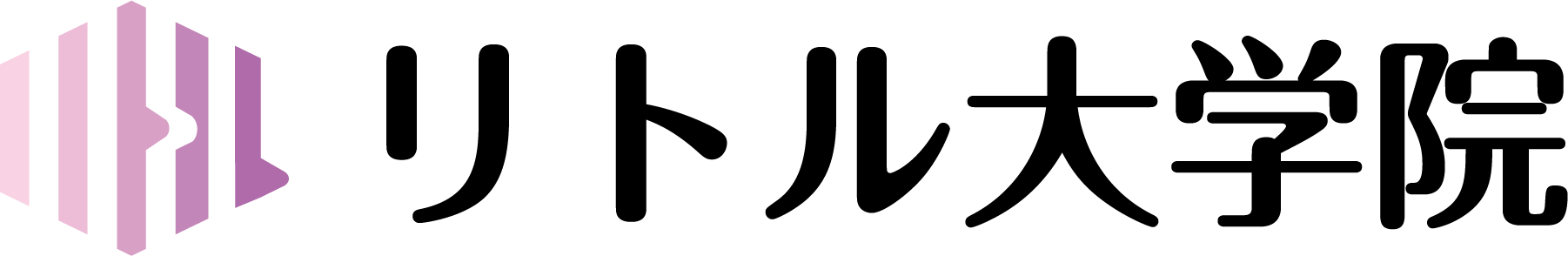課題:ストレート①
■テーマ
毛髪修復のためのストレート
■施術前の髪の状態
・短期間で数回にわたるブリーチ→外国人風カラー(アッシュブロンド)を重ねている。
・ケラチン及びCMCの欠損が見られる。
・年齢(34歳)からしてなんとかキューティクルで維持できている状態。
■目指す仕上がり
・毎日アイロンで伸ばしていて、ストレスがかかる日々ということで、ドライだけでシュッと仕上がるストレートを目指した。
■施術前の髪の状態から考えた施術工程
・癖をしっかり伸ばす。
根本の癖自体はまだアタックできるとして、ハイライトブロンドアッシュの部位にマゼランでしっかり修復させたうえでの還元剤アタックを施します。
① トイトイトーイシャンプーで疎水化→タオルドライ
② アッシュ部位にBYAC+パワードβ(1:1)、全体にヘアマゼラン_ウンをハケで塗布
③ シブミンEX塗布(5倍)
④ チェンジリンス(2分)
⑤ 全体にヘアマゼラン_ドイス塗布
⑥ タオルで無駄な水分を取り、超音波アイロンでスルー。
(50%水分を含んだくらいに調整しながらのスルーです)
⑦ ヘアマゼラン_トレイスを塗布、特にアッシュ部位に多めに塗布。
100℃のアイロンスルー(ノンプレス) → クーリング3分
⑧ しっかり水洗します。
⑨ 還元剤塗布 髪を3部位に分けての塗布 (18分放置)
⑩ 中間水洗
⑪ 中間処理
キトキト(10倍)→へマヘマ(10倍)→中間毛先にリノベーター+リケラミスト1:4
水分をタオルで取り、アジアンムーンを全体に薄くつけて80%ドライ後、
⑫ 180℃アイロン 中間部位よりスルーのみ(プレスはわずかです)
⑬ アンカーローション2 7分×2(2度付け)
⑭ 水洗
⑮ 後処理
ヘマヘマ(10倍)→ポリK(10倍)→キトキト(10倍)→トイトイトーイトリートメント
⑯ ドライ前に毛先にリケラエマルジョン、全体にリケラミスト
⑰ ハンドドライのみで仕上げます。
■各施術工程の意図
①マゼラン:髪の状態と、ゲストの希望で前処理でヘアマゼランを施術。
髪を健康にしてからの還元剤アタック。(髪補強→補修、保護、薬剤パワーコントロール)
②マゼランウンをチョイスした意図
髪の奥底に栄養をしっかりと届かせるのが目的。目いっぱい髪をふやかす。
③シブミンEXをつかう意図
柿渋の脱臭作用で臭いをとる事と、ケラチンと脂質の吸着力up及び軽い収斂を期待。
⑤ヘアマゼラン_マゼランドイスをチョイスした意図
主成分であるアミジノシステイニルケラチンを一週間かけてじっくり浸透させる下地作り
及び家でのトリートメント作用の効果up
⑥超音波アイロン:S-Sの配置を整え、しっかりアミノジノシスティニルケラチンを髪に浸透させる。
⑦アイロン(100℃)をする意味
ガラス状の固い状態からゴム状に変わる温度をガラス転移点といいます。
CMCのガラス転移点は85℃なのでアイロン(100℃)でCMCを溶かし込みます。
この温度の状態変化を活かして、毛髪に成分をしっかりと定着させる。
85℃以上まで加温してCMC成分をダメージホール内に均等に浸透を促していく。
⑨根本-ソニルCA-S+CA-H(1:1) 中間-ソニルCA-S+パワードβ(1:2) 毛先-パワードβ
・根本-還元剤のパワーは要らないが、チオ換算3%は欲しい。
プラス、pHをすこしでも下げる意味での1:1です。
・中間-㏗を下げることに加えてアルカリ度と還元度数を下げる目的。
・毛先-還元がいらないので還元をブロックすることで単品使用です。
とはいえ毛髪は丸裸の状態なの水洗時に化学反応が起きます。
アイロンは毛先まで入れて2剤酸化もさせます。
⑪各処理剤の意図
・ヘマヘマ:1剤封鎖・タンパク質架橋UP
・キトキト:ph調整、キューティクル補修、熱ダメージ予防
・ リノベ+ミスト:しっかり架橋したS-S結合を層体させる。スカスカ状態の毛先に高分子ケラチン
を入れて力を加える目的。
・アジアンをチョイスした意図
アイロンのすべりを良くして毛髪表皮を保護していきます。
⑫中間からプレスを弱くした意図
ダメージがある為、なるべくタンパクの癒着を防ぐためと、過剰に膨潤したダメージ毛への強いプレスによる乾燥収縮を防ぐため。
⑬アンカーの2度付けの意図
アイロン処理後は特に乾燥しているために1度付けだとムラできやすい。2回に分け作用が促進しやすいようにまんべんなくつけることで、ストレートの形成力が高くなります。
■修正を加えた施術箇所
・80%ドライ時に水分が多く残り過ぎたので、少しドライを加えて水分残存調整しました。
■修正の理由
・水蒸気爆発によるアイロンダメージを防止するためです。
■結果および考察
・ほぼ予想どおりのしなやかなノーブローでストレートになりました。
・反省点は、毛先の処理です。画像はカットで収めていますが、ドライのみでストっと馴染ませたいです。






 Prof.榊
Prof.榊渡邉さん、お疲れ様です。プロフェッサー試験までよろしくお願いいたします。
最初からかなりハードルの高い施術で、身が引き締まる思いで拝見させて頂きました。
内容もストレートとマゼランの組み合わせと言うことで、リトルユーザーさんの興味を最も引く内容だと思います。
さて、早速質問させて頂きますが、マゼラン前処理使用はゲストさんの希望とありましたが、ゲストさんの希望が無かったとしてもマゼランを前処理で使っていましたか?



榊先生、初めまして。これからどうぞよろしくお願いいたします。
ヘアマゼラン縮毛矯正は、現在、当店の最も多いメニューになっています。
それだけにまだまだ施術方法などいろんな見解で探っていきたいところであります。
当店は縮毛矯正特化店ということで、マゼランが登場したときからすぐ縮毛矯正施術との組み合わせメニューを考えました。というのもうちはダメージ毛の矯正施術が多いため、常に毛髪のダメージ負担の軽減を考えなくてはなりません。
マゼラン施術のトレイスが酸性のため、100℃アイロンスルーのあとの酸で満たされた毛髪に対しての還元剤アタックにはとても助けられている次第です。
今回もゲストさんの希望が無いとしても、もちろん使う希望を詳しくお伝えして使ったと思います。
その場合はもちろん料金upと施術時間が長くなることもお話して理解を得たうえでの使用になります。



健康毛に極力近づけた状態を作って施術に入ると考えたらマゼランは打って付けですね。
この施術をセミナー披露したとすると受講者さんの興味はマゼランの使いこなし方が気になると思うのですが、マゼラン前処理においてコツや注意点など受講者さんに伝えたいことがあったら教えてください。



はい。
ヘアマゼラン縮毛矯正は4パターンあります。
まず①は、チュートリアルレポートのパターン。
トレイスをつけて100℃アイロンしてクーリングさせて、しっかりお流ししてからの還元剤塗布。
これが一番ベーシックな施術になります。このトレイスをしっかりお流しするというのがキモです。
シャンプーまでは必要ないですが、表面のトレイスは完全にお流しした上で還元剤アタックをさせます。
パターン②は、ウンをつけ、ドイスをつけ超音波アイロン(50%脱水ツインブラシで仮止め)してからの還元剤塗布です。放置時間後、へマヘマ処理してから全体にトレイスをつけて(毛先ダメージ部位はウンを付けます)100℃アイロンスルーしてからドライヤーでドライしてからの180℃ウエットアイロンです。それから2剤酸化です。
これはトレイスを薄くつけるのがキモです。濃くつけるとドライヤーで乾きづらいです。
パターン③は、ウンをつけ、ドイスをつけ超音波アイロン(50%脱水ツインブラシで仮止め)してから
トレイスをつけて100℃アイロンスルーしてからクーリングで、お流ししないで還元剤塗布です。
これは時短バージョンとして良いのですが、トレイスがきちんとムラなく付かないと、還元ムラになります。またしっかりつけると還元剤を浸透させるために、還元時間を伸ばす必要性があります。
パターン④は、リタッチ縮毛矯正のパターンで、根元は還元剤塗布して既矯正部位にマゼラン施術を行うパターンです。このパターンが当店では2番目の多いパターンです。
これはチュートリアルレポートで発表したいと思います。



丁寧、的確な回答ありがとうございます。
各チュートリアルレポートは施術披露だけではなくセミナー披露などで人に伝えるという側面もあります。
受講者さんに実践して頂いて更に結果を出して頂くには各粧剤の使用量、塗布量、NG例などをしっかりと伝えたいですね。
さて次は還元剤について質問させて頂きます。
ソニルCA系をチョイスされていますが、このチョイスの理由をもう少し詳しく教えてください。



はい。
シャンプーあとに、ある程度ポーラスアッシュ部位には癖は伸びましたので、(画像のは来店時の画像です)うねり毛の判断をしました。余力の無いクタクタ状態で伸びていた部分もありましたが。。
ですのでS2環境に多くアプローチをかけるためです。マゼランでの前処理とはいえやはり怖いので、パワードベータで減力をしております。
根元部位は、色はあれど2回ブリーチが入っていますのでS1環境のアプローチはしないで、S2環境にSとHを1:1にして㏗を少し下げての使用です。
それでも通常の還元時間をとれたのもマゼランが効いていると思われます。
あとで、その後の画像を送ってもらえそうなので、添付いたします。



このゲストさんのダメージ具合だとリケラを洗濯するユーザーさんも多いと思いますが、S2アタックということでCAチョイスなのですね。
減力しているとはいえブリーチ部にアルカリ使えるのは、マゼラン前処理あってですね。
反省点でドライのみで毛先を収めたいとおっしゃっておられましたが、どんな処理を加えていたらドライのみで収まっていたと考えますか?



はい。
私は脱水アイロン時は、ツインブラシを使用しますが、80%ドライでのアイロンワーク時に当然根元からスルーさせていくわけですが、水分が必要以上にあるとブラシにより水分が押し出されて毛先に伝わります。毛先を抜いていく瞬間にジュッとなるわけです。瞬間の過乾燥で毛先にパサつき、チリ毛が出たのであろうかと思われました。対策として、アイロン前にキューティクルの剥がれ防止に特トリの接着作用を利用して、そのあとでポリKで吸水した髪の引き締めをすれば良いのかと。
矯正の場合は、毛先が硬くなるのでアフターカットは殆どしないのですが、今回は少しだけ切らせていただき収めました。このようなダメージ毛でもドライだけでストッと収まるように鍛錬いたします。



セミナーなどを数やってると、アレ?ってなっちゃう時あったりしますよね。(私はありました)そんな時その事象の解析と対策を伝えることで受講者さんにも学んで頂けると私は思っております。
今回、なかなか難易度の高い状態でしたが、仕上がりの写真を見ても施術がハマっているのが伺えました。次回もよろしくお願いします。
次に進みましょう。



はい。ありがとうございます。
頑張ります。
課題:ストレート②
■テーマ
潤い感のあるリマサリ縮毛矯正
■施術前の髪の状態
・典型的なうねり毛に加えて毎日セルフでのアイロンダメージ
・約10か月前に酸熱トリートメントでのダメージ
・カラー施術は先月
・しっかりとした髪で太さは中くらい
■目指した仕上がり
・うねりを取りドライのみでシュッと仕上がるしなやかなストレート
■施術前の髪の状態から考えた施術工程
①トイトイトーイシャンプー
②前処理:全体に浸透促進+ミスト(5倍)塗布。コーミング揉み込み後チェンジリンス→全体に3種ミスト(5倍)→毛先BYAC+パワードβ(1:1)→チェンジリンス
③タオルドライ→特トリ(薄く)→超音波アイロンスルー
④1剤塗布:根元EXP+ソニルCA-H(1:1)
中間①EXP+クリームバス(1:1)+アクチベーター(10%)
中間②EXP+クリームバス(1:2)+アクチベータ―(10%)
毛先パワードベータ
⑤18分自然放置→お流し→シブミンEX(5倍)→チェンジリンス
⑥中間処理:ヘマヘマ(10倍)→キトキト(10倍)→チェンジリンス→中間毛先にリノベーター+リケラミスト(1:4)→チェンジリンス→タオルドライ→アジアンムーン
⑦水抜きツインブラシブロー(8割ドライ)
⑧アイロンワーク180℃
⑨2剤 3Ⅾアンカークリーム10分放置→お流し
⑩後処理 ヘマヘマ(10倍)→キトキト(10倍)→チェンジリンス
⑪トイトイトーイトリートメント→仕上げ:リケラミスト
⑫ドライヤードライ
■各施術工程の意図
②前処理:全体に3種混合ミスト5倍 毛先にビヤク+パワードβ(1:1)
・日々のセルフアイロンのダメージ補修に、親水から疎水に転換させる疎水型PPTの3種混合ミスト5倍を使用して穴埋めをさせます。さらに毛先にはビヤク+パワードβをダメージでマイナス電荷の部位にSS結合を導入させます。浸透力upのことも考えて浸透促進ミスト5倍を使用。
③特トリ:接着CMCを導入させ枝毛、チリ毛防止させる。
④1剤:酸性トリートメント部位にはダメージを受け艶感が無く弱い状態になっている。ここに浸透性と還元領域の薬剤
浸透ルートを考え、親水性の球状タンパクのマトリックスへチオを送り込み、そしてミクロフィブリルとミクロフィブリル間の側鎖にアクチベーター(GMT)とシステアミンを浸透させて双方共にバランス良く還元させ、なおかつクリームバスリマサリを混合したものを塗布することで、クリームバスのハチミツが乾燥したダメージ部位に潤いを与えながら還元させることができる。
・毛先部位にはパワードベータの還元無しでダメージ部位の引き締めで補修効果を担う。
⑤シブミンEX:還元剤の消臭及び乳化破壊により、塗布したクリーム成分を洗い流しやすくしてCMC成分の定着向上
⑥中間処理:毛髪内部密度を意識してアイロン時の水分を減らす意識とダメージ補修双方を担う。
・へマヘマ:1剤還元ストップ
・キトキト:㏗調整(アルカリ領域内)と外部補修
・リノベーター+リケラミスト:ダメージ部位のケラチン不足に高分子ケラチンでSS結合をフォローさせる
・アジアンムーンオイル:アイロンワークにおいての熱ダメージの肩代わりと熱による過乾燥予防
⑩後処理:毛髪内の一定の水分量を保たせるため。
・へマヘマ:PPT同士の架橋up
・キトキト:等電点戻し
⑪トリートメント:18MEAで路づくり リケラミスト:ポリアミンAEEによる熱ダメージ防止
■修正を加えた施術箇所
なし
■修正理由
なし
■結果及び考察
ドライのみでスリークに仕上がりました。リマサリのハチミツ成分が潤い感をもたらせた感じです。最後に毛先だけロールブラシを入れています。















今回もよろしくお願いします。
早速質問させて頂きますが、典型的なうねり毛とありましたが、うねり毛と判断された理由を教えてください。



はい。
まず判断基準のひとつとして、カウンセリングで産後に癖毛が強く出てきたと言われていたことです。
これは典型的なうねり毛の判断材料になりました。それともちろん水で濡らして真っすぐになることです。
ところどころですが、波状毛の部位を見受けられました。



工程意図④で、EXPのチオによるS1還元に言及されてましたが、これは波状毛混じりということでの、チオチョイスなのでしょうか?



はい。その通りです。
それともう一つは、うねり部位に対しての効果も兼ねています。パラのS2部位はシステアミンでフォローして、S1部位はチオでフォローですが、高pHや高アルカリですと膨潤する割にダメージに受けがちになります。ですので、アクチベーターでアルカリと㏗を下げて膨潤を抑えつつ、パラの芯の部位をしっかり還元させる役割です。



なるほどです。
うねり毛といえ、S1も意識して、よりクオリティの高いストレートを目指す薬剤チョイス、ミックスと言えますね。
ここは是非受講者さんに、毛髪の見極め方とともに持って帰って頂きたいポイントになると思います。
次の質問ですが、私自身酸熱トリートメントを施された髪をほぼ触ったことがないので私自身が受講者のつもりでお伺いします。
①酸熱トリートメントによるダメージとはどんな物なのか
②その酸熱トリートメントダメージに対しての各リトル粧剤の有用性
この2点の解説をお願いします。2点併せて回答して頂いてもかまいません。



はい。
①酸熱トリートメントも今は色々あるらしいですが、
今回のダメージはS社施術によるものです。
この当初は恐らくグリオキシル酸を使っていたので、このグリオキシルを使う施術で何回も
(3週間ごと3回コースと言ってました)
重ねて施術しますと、髪内部でSS結合とは違う分子内の架橋が起こり、それを重ねていく
中で、どんどん膨潤力が失われて必要な水分量が保てない髪です。
変にパサついた髪になりそれを直そうと思って、ご自分でセルフアイロンを高熱で入れるものだからチリチリになっていることが多いのが現状です。
②リトル商材の有用性ですが、たくさんあると思います。今回は、膨潤力がなく、正しいSS結合量が失われた髪なので、SS量をフォローする意味で一番はリケラリノベータだと思います。
それと正しい水分量を調節できない状態で、かなり乾燥しすぎている状態なので潤い感を保てるリマサリは、良いチョイスだと思います。



写真からもリマサリ効いている感が伺えますね。
緻密な処理剤の使い方も結果に反映されてますね。
大変参考になりました。次に進みましょう。



はい。
次回もよろしくお願いいたします。
課題:ストレート③
■テーマ
硬毛カラー毛をしなやかにするストレート
■施術前の髪の状態
・1か月前のアッシュブラウンカラー 明度8
・セルフカラーとセルフアイロンによるダメージ
・硬毛で量も多め、うねりと広がり。
・ダメージレベル根本2 中間3 毛先4 毛先に削ぎ
・希望はドライだけで済むストレート
■目指す仕上がり
・全体的にまとまりのあるしなやかなストレート
■施術前の髪の状態から考えた施術工程
①トイトイトーイシャンプー
②前処理:全体に浸透促進+ミスト(5倍)→コーミング→揉み込み→チェンジリンス→全体3種+ミスト(5倍)→毛先BYAC+パワードβ(1:1)→チェンジリンス
③タオルドライ
④1剤塗布
・根元2㎝ TIO-H + TIO(2:1)
・中間③ TIO-H + TIO(1:1)
・中間② TIO-H + TIO(1:2)
・中間① CA-H
・毛先 CA-H+パワードβ(1:2)
【内訳】
ネープ1列目 根元TIO-H + TIO(2:1) 中間②TIO-H + TIO(1:2)
ネープ2列目 根元TIO-H + TIO(2:1) 中間③TIO-H + TIO(1:1) 中間②TIO-H + TIO(1:2)
クラウン 根元TIO-H + TIO(2:1) 中間③TIO-H + TIO(1:1) 中間②TIO-H + TIO(1:2)
バング 中間③TIO-H + TIO(1:1)
フェイスライン 中間①CA-H
⑤19分自然放置→お流し→シブミンEX(5倍)→チェンジリンス
⑥中間処理 へマヘマ(10倍)→キトキト(10倍)→チェンジリンス→タオルドライ
⑦ツインブラシブロー
⑧1stアイロン→アジアンム―ン→2ndアイロン
⑨2剤 アンカークリーム(10分)→お流し
⑩後処理 へマヘマ(10)倍→キトキト(10倍)→チェンジリンス
⑪トイトイトーイトリートメント→仕上げ:リケラミスト→ドライ
■各施術工程の意図
②前処理:全体に3種混合ミスト5倍 毛先にビヤク+パワードβ(1:1)
・日々のセルフアイロンのダメージ補修に、親水から疎水に転換させる疎水型PPTの3種混合ミスト5倍を使用して穴埋めをさせます。さらに毛先にはビヤク+パワードβをダメージでマイナス電荷の部位にSS結合を導入させます。浸透力upのことも考えて浸透促進ミスト5倍を使用。
④還元剤:履歴に合わせてアルカリ度バランスを取り、細やかな塗分け
アルカリに働いてもらいたいので、毛先以外は全部ウエット塗布
ソニルH:ソニル(2:1)アルカリ度3.8
ソニルH:ソニル(1:1)アルカリ度3.6
ソニルH:ソニル(1:2)アルカリ度3.3
⑤シブミンEX:消臭及び乳化破壊。塗布したクリームを洗い流しやすくしてCMCの定着向上
⑥中間処理:毛髪内部密度を意識してアイロン時の水分を減らす意識とダメージ補修双方を担う。
・へマヘマ:1剤還元ストップ
・キトキト:㏗調整(アルカリ領域内)と外部補修
⑧アイロンワーク:Wアイロン。全体にカラーによるアルカリ残留でぼわっとして引っ掛かりがあるので、ドライで乾かしても毛羽が出来る。ここで急激に水分を抜くとビビったり毛羽立ちが残りやすい。したがってゆっくり水分を抜くために2回に分ける。1度目のアイロンは真っすぐにすること。
2度目はアジアンムーンオイルをつけて膨潤を抑え水抜きアイロンが主である。
アジアンムーン:アイロンワークにおいての熱ダメージの肩代わりと熱とアルカリによる過膨潤予防
⑩後処理:毛髪内の一定の水分量を保たせるため。
・へマヘマ:PPT同士の架橋up
・キトキト:等電点戻し
・トイトイトーイトリートメント:18MEAで路づくり
・リケラミスト:ポリアミンAEEによる熱ダメージ防止
■修正を加えた施術箇所
なし
■修正理由
なし
■結果及び考察
ドライのみで仕上げました。毛羽は抑えられましたが若干硬さが出たかもしれません。
しなやかさとのバランスが課題です。















今回もよろしくお願いします。
施術行程の意図②で、「親水から疎水に転換させる疎水型PPTの3種混合TIO-H + TIO(1:1)を使用して穴埋めをさせます。」と記述されていますが、「」内の部分をもう少し詳しく教えて頂けますか。



はい。榊先生、これは誤って編集されてしまったみたいです。
正しくは、
●前処理:全体に3種混合ミスト5倍 毛先にビヤク+パワードβ(1:1)
「日々のセルフアイロンのダメージ補修に、親水から疎水に転換させる疎水型PPTの3種混合ミスト5倍を使用して穴埋めをさせます。さらに毛先にはビヤク+パワードβをダメージでマイナス電荷の部位にSS結合を導入させます。浸透力upのことも考えて浸透促進ミスト5倍を使用。」と送っております。
失礼をいたしました。



なるほど、そうでしたか 還元を利用してPPTを効かす高等テクニックかと考えを巡らせておりました。
では同じ施術行程の意図②についてお伺いしますが、私の場合、3種ミストとBYACを併せて使用する場合、BYACで疎水化が出来たと感じてから、3種ミストを導入というのがマストなのですが、渡邉さんは3種ミスト→BYAC+パワードβと使っておられましたが、この順番は何か理由がありますか?



ありがとうございます。
先にBYACですか、とても参考になります。
私の場合、矯正で一番大切なところにはナチュラル感を大切に考えています。
少し言葉古いですが、素髪感といいましょうか。なるべく柔らかくそして芯のある
しなやかさをいつもゲストには強調しております。
BYACの疎水化は、シスチン補強をして毛髪強度をとても高めてくれます。
また高アルカリの膨潤を抑えるには絶好の前処理剤です。
ただできるなら自然風合い感をそのまま保てるであれば、そして使わなくても良いのであれば使用しないで、3種のみでいけるならと思っています。
3種を先につけて、感触を確認してからもう少しいけるというときに、BYACを導入しています。
そこまで必要しないのであれば、3種のあとに特トリ使用にしております。



とても腑に落ちる回答です。私も大変参考になりました。
処理剤はもちろん結果が大事ですが、使い手の考え方が一番大事だと考えます。
今回の回答は、受講者さんに是非持って帰って頂きたいところですね。
もう1つこの項目で質問させて頂きます
BYACにパワードβを併せてますが、パワードβをチョイスした理由を教えてください。



はい。
これは前回の理由と繋がるとこでもあるのです。BYACのグアニジル基はマイナスのアミノ基に強力に張り付きまたイオン結合でSHを増やして強度が上がるので、特に吸水毛には良いのですが、私自身は、縮毛矯正自体にナチュラル感を大切にしてるところで、毛先部位には(特に毛先にBYACを使います)自由度を求めています。
縮毛矯正は特に根元の癖は伸ばさなければいけないところで、中間から根元をストレートにすればするほど毛先は逆モーションの動きをします。例えばショートボブのような短ければまだ毛先を内巻きに矯正できても、髪は硬質な素材ではなく、髪はばらつくのでロングになればなるほど矯正力が高いと外側に跳ねます。根元から中間までのストレート効果と毛先の強化のモーションはかかりますが、そのまま乾燥しないのが着地点であると考えます。
なので、毛先ほど固定しないでなるべく自由度をもたせるのを常としていますので、矯正においてはBYACを半割にして柔らかくさせておきたいという考えです。そこで、何で割るかということですが、㏗も酸性で収斂性も高いパワードβが一番良いと思ってます。
例えばパーマで毛先に力を持たせたいときには、fullでBYACを使用して曲げのモーメントを作っています。



そうですね。
毛先内部の空洞化、吸水性の高まりを考えると、収斂を意識した薬剤チョイスになりますね。
今回もこの項目から質問させて頂きますが、浸透促進導入後、3種BYAC導入後それぞれチェンジリンスされていますが、チェンジリンスをする狙いと効果を教えてください。



はい。
チェンジリンスの狙いは、処理剤成分を髪に均一に行き渡らせることです。お湯を溜め髪全体にお湯を流しながら浸透圧で全体に行き渡らせます。
効果は、処理剤の定着です。ボールにお湯を貯め処理剤が落ちていきます。するとお湯は毛髪内部より成分濃度は濃い状態になります。そのお湯を指でかけるときにクレンジング作用、つまり指でぬぐう物理的な力により毛髪内部に向かい成分浸透が加速します。濃度が薄い方にながれる浸透圧現象です。チェンジリンスによりお湯が髪に浸透して膨潤作用が起こり可能になります。



処理剤成分を均一に行き渡らせ、処理剤の定着を図るということで、狙い、効果の回答は十分に理解できます。
ただ、解説のところで「ボールにお湯を貯め処理剤が落ちていきます。するとお湯は毛髪内部より成分濃度は濃い状態になります。」とありますが、浸促、3種ミストそれぞれ導入しているので、毛髪内の方が濃度が高いように思われるのですが、如何でしょうか?



はい。
浸促の効果がどれくらいあるのかは数値的に不明確ですが、それでも3種は疎水性が高く毛髪内が親水性であるなら、結びつきはまだ弱く緩い構造であると思います。
例えば疎水性同士であれば、周りが水分子安定化させるため疎水性分子がくっ付き疎水性相互作用になります。したがって毛髪内に入りきれない3種分子は、ボール内に満たされることになります。するとボール内の水分子はクラスレートが壊れて、エントロピーが増え更に毛髪内に入り込こむことが可能になると思います。いかがでしょうか?榊先生。



導入した3種ミストは疎水性が高いので、親水部位に到達、着床してないことも考えられる。その親水部位に関しては、ボール内の成分濃度の方が濃いと考えられる。
と、解釈したのですが、どうでしょうか?



はい。榊先生、そうです。そう捉えました。



チェンジリンスは、「処理剤成分を均一に行き渡らせ、処理剤の定着を図る」為の突っ込んだ一手ということですね。
私の臨店やセミナーなどの経験で、作業(この場合チェンジリンス)項目を追っかけることや、その作業動作に一生懸命になるあまり、作業、作業動作の目的がおざなりになってしまう美容師さんを多く見て来ました。今回の質問が、もし、受講者さんからだとしたら答え方も違っていたかもしれませんが、渡邉さんの前処理において、かなり重要なポイントに感じられるので、しっかり発信して頂きたいところですね。
今回は1剤について質問させて頂きます。
先ずは、緻密な塗り分けを拝見させて頂いて頭が下がる思いです。
この緻密な塗り分けは、薬剤ミックスのアルカリ度計算から来ているものと考えますが、
毛質、ダメージレベルとアルカリ度に関する目安みたいなものはありますか。



はい。
毛質、ダメージレベルとアルカリ度についてですね。
私は、ダメージレベルに対しての薬剤選定表をカラーの有無とカラーダメージの高低を基に
作りました。
薬剤は、ソニルチオ(H)、ソニルチオ、EXP、CA-H、CA-S、パワードβの6種類。
パワー9~パワー0までの10段階です。
パワー9~パワー7までノンカラーレベル
パワー6~パワー4までカラー毛レベル
パワー3~パワー0までダメージレベル
で分けています。
アルカリ矯正の場合、ダメージにより過剰に膨潤するので、
アルカリ度で還元剤をランク分けをしています。
今回の毛髪の場合、
根元2㎝は新生毛なので、
ノンカラーレベルのパワー7 ソニル(H):ソニル=2:1
中間部を毛髪のダメージ状況により、3段階に分けました。
中間③部位をカラー毛レベルのパワー6 ソニル(H):ソニル=1:1
中間②部位をカラー毛レベルのパワー5 ソニル(H):ソニル=1:2
中間①部位をダメージ毛レベルのパワー3 CA-H(もしくはCA-S)
毛先部位をダメージ毛レベルのパワー1 CA-H(もしくはCA-S):パワードβ=1:2
です。
ちなみに
パワー9のアルカリ度は4
パワー8のアルカリ度は3.85
パワー7のアルカリ度は3.8
パワー6のアルカリ度は3.6
パワー5のアルカリ度は3.3
パワー4のアルカリ度は2.8
パワー3のアルカリ度は2.0(1.8)
パワー2のアルカリ度は、1.0(0.9)
パワー1のアルカリ度は、0.6(0.4)
パワー0のアルカリ度は、0
*( )内はCA-Sにした場合です。



丁寧な回答ありがとうございます。
そして、思考と検証の賜物であろうスケールの公開ありがとうございます。
今回は渡邉さんのこの回答を通して、「皆様に言いたい、ストレートというリスクを伴う仕事は、ここまで思考を巡らせ臨むものなんですよ」と私が言いたくなりました。
ストレート施術だけでなく、剤は漠然と使うのではなく、しっかり思考して使うということを伝えて行きたいですね。
今回の質問ですが、受講者さん、若しくはこのチュートリアルを見ている人がいるとして、おそらく出るであろう質問なんですが、所謂、軟化チェックはどうされてますか?
1剤放置時間設定と連動しているようなら併せて教えてください。



はい。
軟化チェックはその名の通り、髪が柔らかくなったか、まだ硬いかをチェックすること。
私は、コームの端に毛束を数本巻き付け、髪がコームからスルっと逃げると「軟化不足」
コームにくっつき逃げないと「軟化OK」と判断しています。
もし軟化不足と出ましたら、不十分な部位にEXPを再塗布します。
ノンカラーで18分、カラー毛で15分、ダメージで13分放置目安です。
放置時間を伸ばすより再塗布のほうのが時短になりますし確実です。
ただ、軟化と還元は違います。軟化OKでも還元不足はありますし(特にうねり毛)軟化無くても還元OK
もあります。特にアルカリ軟化はアルカリ度とpHで短い時間でも軟化します。
縮毛に関しては軟化と還元の両方が必要で、また酸性還元とアルカリ還元でも変わります。



追加の質問になりますが、今回の場合、19分の放置後に軟化テストでしょうか?



はい。15分で軟化チェックして一応保険の4分追加で19分です。再塗布までは必要無しの判断です。



縮毛矯正の講習した時、必ずと言っていいほど出る質問が、1剤放置時間設定と軟化の見極めですよね。
前回の質問、回答併せて改めて自分のスケールを持っているのが大事であると私自身再認識させて頂きました。
今項目最後の質問にさせて頂こうと思いますが、結果考察で、「若干硬さが出たかもしれません」とありましたが、改善を図るための想定をお聞かせください。



はい。
今回軟らかさを出すために、Wアイロンで2回に分けて水抜きをしたのですが、2回目のアイロン時に髪に膨潤があり水抜きが急激に働いたのが原因かもしれません。酸性矯正と違いアルカリ矯正は急に水分が抜けるとどうしても硬くなりやすいです。改善を図るために1stアイロンで若干しっかり目に抜いていくこと。2stアイロンでのオイルを付け膨潤を抑えてのアイロンワークが課題です。



そうですね。矯正でしなやかさや素髪感を求めるなら膨潤を極力抑える事が必須だと私も考えます。
中間処理で、脂質導入(リケラエマルジョン、パワードβなど)後、ポリKを使うというのは如何でしょうか?



はい。まさしくそうで、膨張している髪にはアイロンかけてもあまりいい結果が出ないので、
エマルジョン→ポリKは、うってつけだと思います。ありがとうございます。早速明日実践します。



はい。それではストレートチュートリアルはこれにて終了ということでお疲れ様でした。
渡邉さんの緻密な仕事、考察には私も大いに学ばさせて頂きました。
次に進みましょう。



ありがとうございました。
榊先生の脂質導入の施術、大変勉強になりました。Skyspaの武器になります。
次回も楽しみにしています。
よろしくお願いいたします。
課題:パーマ①
■テーマ
矯正毛に対してのWクリープでしなやかなパーマデザイン
■施術前の髪の状態
・半年前に縮毛矯正
・3ヶ月前に20レベルのライトナー
・中間毛先は日々のホームアイロン
・太さは中くらいのタンパク質変性毛
■目指す仕上がり
・ドライのみでしなやかに手ぐしで流せる
・緩めのやわらかなウェーブ
・すぐに取れない
■施術前の髪の状態から考えた施術工程
①プレカット
②トイトイトーイシャンプー
③前処理:お湯を貯めてBYAC原液を溶かして全体にチェンジリンス→全体に3種+ミスト5倍を揉みこみチェンジリンス
④セット面で全体に特トリを付けて、超音波アイロンスルー
⑤ワインディング
⑥1st還元:クリープHを塗布、自然放置1分
⑦シブミンEX5倍塗布→中間水洗⑴
⑧中間処理⑴:へマヘマ10倍
⑨クリープ⑴
⑩中間処理⑵:リノベーターローション:リケラミスト(1:4)塗布→5分放置→カールチェック
⑪2nd還元:リノベーターローション:クリープS:アクチベーター(5:5:1)塗布、自然放置6分
⑫シブミンEX5倍塗布→中間水洗⑵
⑬中間処理⑶:へマヘマ10倍
⑭クリープ⑵
⑮中間処理⑷:いきいき5倍塗布→2分放置→ポリK5倍塗布→3分放置→カールチェック
⑯2剤:B2ローション7分+7分の2回付け
⑰後処理:へマヘマ10倍→キトキト10倍→チェンジリンス
⑱トイトイトーイトリートメント
⑲仕上げ:全体にリケラミスト→ドライヤードライ→全体にリケラエマルジョンを軽くつけてフィ二ッシュ。
■各施術工程の意図
③前処理
半年前の縮毛矯正に加えて毎回のホームアイロンのダメージ補修に親水から疎水に転換させる為にお湯を貯めて全体にBYAC原液を混ぜ髪に行き渡らせながらチェンジリンス、毛髪強度が上がり疎水化したところで、全体に3種+ミスト(5倍)をつけてチェンジリンス。
④特トリ
接着CMCを導入させて、スムーズなパーマ剤の通り路の確保。
超音波アイロン:塗布のみでは剤が浸透しにくいので、音波による振動を与え促進させます。求める質感までになれば良いと思うので、同時に水分コントロールも行います。
⑥1剤
髪は半年前に縮毛矯正をかけておりタンパク質変性をしている。ケラチンタンパクの欠損の激しいSS量の少ない髪には、弱い薬剤そして大きなロッドではカール形成が不可能。この少ないSS量に取りこぼしないように還元と再結合をかけたいということ。ダメージ毛ほどマトリックスは欠損しておりソニルHを使用すれば瞬間でS2の芯まで深部還元させることができる。還元したら素早く水洗で還元剤を抜き取ります。還元時間が短いほどパーマ剤は内部残留しないので、毛髪のダメ―ジロスに繋がります。しっかり水洗させたあとには、2st還元でpH7.2 程度の還元で毛髪表面のみ還元をかけます。低pHのシスアミであれば毛髪表面のSSにアプローチが可能です。
またアルコール主体のソニルであれば揮発しますので水洗で残留アルカリが軽減できます。
あとは最終クリープで粘性及び弾性を最低限残したままクリープ期に内部移動をできるくらいゆっくりとCMCをずれさせてウェーブ効率を確立させていきます。
パーマ剤
・ソニルクリープH pH8.5
・ソニルクリープS:リノベーターローション:アクチベーター(5:5:1)トータルでpH7
・リノベーターローション:高分子のAEDSでダメージを受けたケラチンが減少したダメージ部位にSS結合を導入。
・アクチベーター:リノベーターを活性化させるGMT酸性還元剤
⑦中間処理
・シブミンEX:還元剤消臭
・へマヘマ:1剤還元ストップ
・キトキト:㏗調整と外部補修
⑨⑭クリープ⑴⑵
髪への負担を考慮して段階を踏まえて処理剤使用する。
⑩中間処理⑵
リノベーターL+リケラミスト(5倍):ダメージ部位のケラチン不足に高分子誘導ケラチンでSS結合のフォロー
⑧⑬中間処理⑴⑶
へマヘマ:PPT同士の架橋を助ける
⑮中間処理⑷
・いきいき:高低双方のケラチンで髪の強さとハリコシのフォロー
・ポリK:ポリフェノールの作用で髪の引き締め作用、カール形成の確立。
⑯2剤酸化
B2ローションでしっかりゆっくり酸化させます。
⑰後処理
・ヘマへマ:PPT同士の架橋up
・キトキト:等電点戻し
⑱トリートメント
18MEAで路づくり
⑲仕上げ
・リケラミストポリアミンAEEによる熱ダメージ防止
・リケラエマルジョン:結晶性コレステロールでCMCの整え
■修正施術箇所
なし
■修正理由
なし
■結果及び考察
とても柔らかなカールでした。あまり硬くなり過ぎても良い感じがしないので(しなやかさという面で)成功例だと思います。



















お待たせ致しました。今回もよろしくお願いします。
前処理から質問させて頂きます。
「お湯を貯めてBYAC原液を溶かして全体にチェンジリンス」とありますが、BYAC直接塗布→チェンジリンスと、狙いや効果で違いなどありますか。



はい。今回もよろしくお願いいたします。
ゲスト様の毛髪状態から言えば、矯正毛ですのでタンパク質変性は否めない。したがって兎にも角にもBYAC原液を使いSS導入に確実にフォローしてもらえることです。
当然毛先の強度は無くて、いつもならBYACにパワードβを混ぜて使うのですが、前回のチュートリアルの榊先生の脂質導入の方法を取り、ダイレクトにBYACが反応できるようにBYAC原液を髪に行き渡らせながらチェンジリンスしました。
そうすることで、中身をしっかり詰めたことによりキューティクルも強化できます。
毛髪の変化を直に感じて、髪はその時々で条件や質感が変化しますので、大切なところは手で感じ取れるかだと感じます。1回では効果が薄いので、チェンジリンス後再びBYACを投入して疎水化させました。毛髪は硬くなりキシキシしてきたところで疎水化を確認できたところで、3種ミストへ移行しました。



なるほどです。
仰るように毛髪の状態改善を感じながらの作業はかなり重要なポイントですね。
慎重に求める状態まで持って行く場合、チェンジリンスが肝になりますね。
1剤についてお伺いします。
施術行程の意図を読ませて頂き、大いに納得できました。
これを一般ユーザーさんに伝える場合、2回の還元→クリープは必ずでしょうか?
1回の還元→クリープで求めるカールに達していたら1回の還元→クリープで終ることは考えられますか?



はい。クリープ後カールチェックで確認して、ダレの無い本当に求めるカールに達していれば
そのまま中間処理して酸化工程へ進めば良いと思います。
しかし1回目のクリープ後のカール形成が不十分であれば、セカンド還元として中性域の還元仕様で2次膨潤を抑えられ、まして2回工程に分けWクリープで更にしっかりカール形成を確立することができます。
今回は矯正毛という毛髪内部がタンパク質変性されている髪ということで、1回目だけだと1分ではしっかりとカールが成り立ちませんでした。かといって1分以上では毛髪が持たないことの見解でした。
毛髪損傷が激しく著しく弾性の少ない髪ですので、アルカリ還元剤はとにかく短時間で抜き取り、S2を還元させたら、リノベーターを使いSSを増やし骨格を作ります。2回目の還元でシステアミンはアミノ基がありますので、中性域では+に帯電するので毛髪表面を還元できます。1回目で内側を、2回目で外側をと分けて還元することで矯正ダメージ毛でも、穏やかですがしっかりとカール形成を達成させます。



毛髪の状態、強度もしっかり言及されていて、還元も内深部、表面に向けた剤のチョイスが為されていると伺えます。
よって、今回の毛髪に対しては2度の還元が必然と言って良いでしょうね。
2nd還元でアクチベーターもミックスされていますが、役割りは何でしょう?



はい。
ソニルクリープSの還元濃度(チオ換算)を上げて、そして㏗を下げるのが目的です。
ソニルクリープS:リノベーターローション:アクチベーター(5:5:1)でそれぞれ(10g:10g:2g)です。トータルで22gです。
還元濃度は、4.9
アルカリ度は、0.5
㏗は7.5程度です。



そうですね。
還元剤濃度を損なうことなく、アルカリ度を下げ、過膨潤を避けて最大限効率的な還元を図るには、アクチベーター混ぜが持てこいだと思います。
剤のスペックを数値化されて臨まれているのも素晴らしいと思います。
今回はクリープと中間処理についてお伺いします。
⑨⑩、⑭⑮でクリープ→中間処理になっていますが、この順番の意図を教えてください。



はい。
最初のクリープでは、開錠した毛髪内のSS結合の組み換えのためAEDSがSS結合を増やしていく役目をリノベーターローション:リケラミスト(1:4)で取ってクリープさせて穏やかにズレさせていきます。この時のカールチェックが最初の画像です。確かにカールはかかっていますが力が無くテロンとした様子です。しかしSSが増えビルドアップした感じは見受けられました。このままでは弱いと感じましたので、セカンド還元で表層にアプローチしました。次のクリープでは、「いきいき」で力のない毛髪に」ハリコシを付ける役割をしてもらいます。私のパーマ工程では「いきいき」無しでは考えられません。必ず工程内に入れることでしっかりのカール形成補助をしてくれるのが「いきいき」です。最後にポリKでケラチンとCMCを引き締めて内側からくっ付けていきました。2番目のカールチェックの画像がその下の画像です。収斂した様子が出ているかと思います。OKでしたのでブロム酸でゆっくりと酸化工程に入りました。



すみません、もう一つ質問させて下さい。
各クリープの時間はどのくらいとっておられますか?



はい。
1回目は5分です。2回目も5分です。



確認質問が続いて申し訳ないですが、⑩と⑮の中間処理内に記述されている放置時間がクリープの時間と理解してよろしいですか?



はい。その通りです。カールチェック後に次の工程に進んでおります。



クリープ(時間経過放置)の後、中間処理をされているように読みとっておりました。
すみません。
前述のお答えから、しっかりと狙いを設定し、それに伴う剤のチョイスがあり、状態を見極めながらの処理を施されていることが理解できました。
今回も簡単な毛髪状態ではなかったと思いますが、狙い通りのしなやかなカールが達成されているのは素晴らしいと思います。
次に進みましょう。



はい。ありがとうございました。
判りづらくてすいませんでした。
次回もよろしくお願いいたします。
課題:パーマ②
■テーマ
セルフカラーによるエイジング毛へのSS増強3Dカール
■施術前の髪の状態
・余力の無いクタッとしたダメージ状態
・白髪ゆえに毎回ホームカラーをしている
・太さは中くらいのエイジング毛
・半年前にパーマ
■目指す仕上がり
・ドライしてサッと手ぐしで流せる
・乾かすのみでまとまる柔らかいウェーブ
・トップにフンワリボリューム感
■施術前の髪の状態から考えた施術工程
①トイトイトーイシャンプー
②前処理:シャンプーボールにお湯を貯めてBYACを溶かして毛先に付ける→3種混合ミスト5倍塗布→チェンジリンス→特トリ→シブミンEX塗布→チェンジリンス
③セット面で超音波アイロンスルー
④ワインディング
⑤圧縮蒸気
⑥1剤:ソニルクリープH を塗布、自然放置1分半
⑦しっかりと中間水洗
⑧中間処理:へマヘマ10倍→キトキト10倍
⑨クリープ:リノベータローション:アクチベーター:リケラミスト(20:1:10)を塗布→7分自然放置→へマヘマ塗布→いきいき塗布→5分自然放置→カールチェック→ポリK 5倍塗布→3分放置(クリープ時間15分)
⑩2剤:B2ローション7分+5分の2回付け
⑪ロッドアウト→お流し
⑫後処理:へマヘマ10倍→キトキト10倍→チェンジリンス
⑬トイトイトーイトリートメント
⑭仕上げ:全体にリケラミスト、毛先にリケラエマルジョン→ドライヤードライ→全体にアジアンムーンオイルを薄くつける
■各施術工程の意図
②前処理:全体に3種混合ミスト5倍、BYAC原液
・毎回のセルフカラーのアルカリダメージ補修に親水から疎水に転換させる疎水型PPTの3種混合を利用して穴埋めをさせます。中間~毛先部位にはBYACを少しずつ付けることで、強度を確かめながら調整して導入していきます。
・シブミンEX:薬剤の使用感を最小限にしてキューティクルの疎水化
・特トリ:接着CMCを導入させて、スムーズなパーマ剤の通り路の確保
③超音波アイロン:塗布のみでは剤が浸透しにくいので、音波による振動を与え促進させます。求める質感までになれば良いと思うので、同時に水分コントロールも行います。
⑤圧縮蒸気:還元処理剤等、浸透促進のためスチームを当て毛髪のプレ膨潤の促進を行う。
⑥1剤:ソニルクリープH
ダメージを考えれば当然クリープSをチョイスすべきですが、ダメージ毛ほどマトリックスは欠損していますので、Hを使用すれば短時間でS2の芯まで還元させることができます。還元時間が短いほどパーマ剤は内部残留しないので、毛髪のダメ―ジロスに繋がります。しっかり水洗させたあとは粘性及び弾性を最低限残したままクリープ期に内部移動をできるくらいゆっくりとCMCをずれさせてウェーブ効率を確立させていきます。
⑧中間処理:
・へマヘマ:1剤還元ストップ
・キトキト:㏗調整と外部補修
⑨クリープ:髪への負担を考慮して段階を踏まえて薬剤使用する。
・リケラリノベータローション+アクチベーター(20:1)ダメージ部位のケラチン不足に高分子誘導ケラチンでSS結合のフォロー(リノベーターケラチンをアクチベーターで活性化させてからの使用)塗布15分くらい前にリノベーターケラチンを活性化させておく。
・ミクロクリープを狙いクリープタイムを15分置きます。
・へマヘマ:PPT同士の架橋を助ける
・いきいき:高低双方のケラチンで髪の強さとハリコシのフォロー
・ポリK:ポリフェノールの作用で髪の引き締め作用、カール形成の確立。
⑩2剤酸化: ・B2ローションでしっかりゆっくり酸化させます。
⑫後処理:
・ヘマへマ:PPT同士の架橋up
・キトキト:等電点戻し
・トリートメント:18MEAで路づくり
・リケラミストポリアミンAEEによる熱ダメージ防止
・リケラエマルジョン:結晶性コレステロールでCMCの整え
■修正施術箇所
なし
■修正理由
なし
■結果及び考察
思ったよりカールが出て、独特の弾力感が得られました。リケラリノベーターの活性を直に感じることができました。















今回は、先ず全体の感想から述べさせて頂きます。
◎前処理
いつもながら、的確な考察の元 状態、感触を確かめながら強度アップし健康毛に近づけておられるようで、施術、意図ともに言う事無しですね。
◎1剤以降
写真からして、求める仕上がりになっているのが解ります。
1剤以降の施術、処理が正解であることを示していますね。
ですので、今回はお考えを伺いたく質問させて頂きます。
使う1剤を決めてから前処理を設計されましたか?それとも前処理後の毛髪状態から使う1剤を決めましたか?



はい。②の前処理から③の超音波アイロンまでの間に決めました。
前処理で毛髪強度も上がり、圧縮蒸気の力も加味して状態を見てクリープHに決定しました。
もしこのケースでクリープSを選択するとロッド径はもっと細くなければいけないし、放置時間も長くなり曲げの応力がかかり歪ませることになり、カールデザインがしづらくなると思いました。



疎水化前処理の重要性を再認識させて頂けるお話しですね。
安易な決め打ちではなく処理を施した毛の状態を見極めながらの薬剤チョイスと施術、素晴らしいと思います。
今回も意見交換的な話しとして聞いて下さい。
テーマがSS増強3Dカールということで、リノベーター+アクチベーターで還元を行うという考えはよぎりませんでしたか?



はい。全くよぎりませんでした。
今回の施術テーマとして、SS量の増強をさせておきたいということがとてもありました。
恐らくは、再びご自分の家でホームカラーをすることが判っていますので(毎度のことなので)
なるべくならSS量を増やしておいてあげて、カラーダメージが起きたとしても(セルフカラーにおいて)、次回の施術に少しでも繋がるように施術プランを立てました。なのでリノベータ+アクチベーターはあくまで還元でなくSS量の加味することで徹してもらいました。
リノベータ+アクチベーターの還元ですと、アクチベーターの濃度の高い設定が必要になり高濃度のアタックが増えすぎる感じがありました。



なるほどです。
前処理で毛髪強度の復旧を確認してから短時間S2還元がキモということですね。
もし、クリープ後のカールチェックでカールが足らないとしたら前回同様に表面還元の行程が加わることになりますか?



はい。
表面還元が全く無いかというと場合によってはあり得ますが、今回は無いです。
カラーダメージ対策として、毛髪体力を残しておきたい為です。
クリープ後のチェックカールで足らない場合は、応力緩和に毛髪内部のコルテックスを動かすため水をかけて、圧縮蒸気か、もしくは遠赤をかけてクリープを進ませます。カールが出ましたらポリKで収斂させて環境を整えます。



今回は1剤の時間の短さが際立つお仕事でした。
そして、クリープとSS導入の重要性を見せて頂けたと思います。
次回も楽しみにしています。
次に進みましょう。



榊先生、
次回からも更に気を引き締めて挑みます。
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
課題:パーマ③
■テーマ
毛先1カールのフェミニンパーマ
■施術前の髪の状態
・10ヶ月前にデジタルパーマ
・まめにセルフで毛先カールアイロンセット
・前回はサロンのカラーリング
・細くてキューティクルがしっかりしている
■目指す仕上がり
・毛先1カール程度のカールアイロンの補助パーマ
・前回はデジタルで大きいカールをしたが、今回は極力広がりを抑えてのコールドでの1カール
・コールドPでプリンと毛先のみにかける。
■施術前の髪の状態から考えた施術工程
①プレカット:デジタル部位を毛先約10センチほどカット。ローでレイヤーを入れた。
②トイトイト―イシャンプー後ボールにお湯溜めて、BYAC原液を溶かして毛先につける→シブミンEX5倍→CR
③前処理:全体に3種ミスト5倍・特トリ→超音波アイロン
④ワインドロッド1回転半 1剤:クリープH塗布後、圧縮蒸気で3分
⑤中間水洗→中間処理:へマヘマ20倍
⑥クリープ→いきいき:リノベータ―:リケラミスト(1:1:4)塗布10分でカールチェック→ポリK5倍塗布2分放置
⑦2剤アンカー10分
⑧ロッドアウト→お流し
⑨後処理:ポリk5倍→へマヘマ10倍→キトキト10倍→チェンジリンス
⑩トイトイトーイトリートメント→お流し
⑪アウトバストリートメント:リケラミスト→リケラエマルジョン
■各施術工程の意図
③前処理:
・随時ホームアイロンのダメージ補修に親水から疎水に転換させるためにお湯溜めて毛先にBYAC原液を混ぜ髪に行き渡らせながらチェンジリンス、疎水化させる。指で感触を確かめながら行う。
・シブミンEX:薬剤の使用感を最小限にしてキューティクルの疎水化と消臭
・3種ミスト5倍:デジタルダメージ補修に親水から疎水に転換させる疎水型PPTの3種混合を利用して穴埋めをさせます。
・特トリ:接着CMCを導入させて、スムーズなパーマ剤の通り路の確保
・超音波アイロン:塗布のみでは剤が浸透しにくいので、音波による振動を与え促進させます。求める質感までになれば良いと思うので、同時に水分コントロールも行います。
④1剤:キューティクルがしっかりしているので、クリープHを使用して少し長めに浸透させる時間を取ります。
⑤中間処理:へマヘマ20倍 1剤還元ストップ、ゆっくりと還元封鎖の為ヘマへマ20倍です。
⑥クリープ:不活性リケラの2つの活用性、毛髪内部の歪みをとるSS-SH交換反応を司るミクロクリープの活性化。SS-SH酸化還元反応を利用する活性化です。12分クリープ(1剤と合わせて15分)
・いきいき:高低双方のケラチンで髪の強さとハリコシのフォロー
・リノベーター+リケラミスト:ダメージ部位のケラチン不足に高分子誘導ケラチンでSS結合のフォロー
・ポリK:ポリフェノールの作用で髪の引き締め作用、カール形成の確立。
⑦アンカー:ブロム酸でしっかりと再結合させます。
⑨後処理:
・ヘマへマ:PPT同士の架橋up
・キトキト等電点戻し
⑩トイトイトーイトリートメント:18MEAで路づくり
⑪リケラミスト:ポリアミンAEEによる熱ダメージ防止
・リケラエマルジョン:結晶性コレステロールでCMCの整え
■修正施術箇所
なし
■修正理由
なし
■結果及び考察
意外に難しいのが毛先1カールパーマ。弱いとダレるし強いと跳ねてしまう。ジャストが良いのですが今回少し強いくらいでした。もう少し緩くても良いのかと・・。













大変お待たせしました。今回もよろしくお願いします。
今回、クリープ時は不活性リケラ処理になっていますが、活性と不活性の使い分けの判断のコツや見極め方などあったら教えてください。
受講者さんからの質問の体でお答え頂けたらありがたいです。



はい。わかりました。
「まずはリケラリノベーターの活性化と不活性化の違いを判りやすく説明します。
リケラリノベーターの主成分はAEDSケラチンです。これはSS残基を持っている高分子のケラチンのことです。
ここで言う活性というのは、このリノベーターのSS残基を予めアクチベーターという酸性還元剤(GMT)に混ぜて還元させ反応性の高いSH残基を持つ高分子ケラチンに変化させます。
10分~15分かかりますので、前もって混ぜておきます。
このことを活性化と表現しています。
静止状態にあるSS残基がアクチベーターの力で活動力の高い高分子ケラチンに生まれ変わります。
この活性化された高分子ケラチンを毛髪内部へ入れると、髪内部のSH基とこの高分子ケラチンのSH基が結合することになります。したがって元々の髪内部のSS結合を介せる数が増えることになります。
不活性というのは、リケラリノベーターのAEDSケラチンをSS残基のまま毛髪内部へ入れていきます。アクチベーターは使いません。
SS残基のままなのでSS/SH交換反応のときにこのAEDSケラチンは、活動力の高いケラチンではありません。SS基のままなので交換反応がゆっくりとしか進めません。ですからSS/SH交換反応を用いるのに時間が必要になります。
●使い分ける判断のコツとすれば、活性化させる必要のある例えば、パーマ、ヘアカラー、ストレートなどのダメージのあるSS基が流出した髪や加齢で痩せてしまった髪(ケラチン減少のため)、またSS基が少なくて特に根元と毛先のダメージ差があり、均一にパーマウェーブがかからないとか、カラーにムラが出るなどの弱々しい状態に力を発揮させるので、髪強度を持たせたい場合に使うのが一番効果的です。髪を見極める基準の所もここです。
イメージとしては毛髪の美容整形手術です。
●不活性に使う場面としては、まず一番は、活性化するアクチベーターを使わないので毛髪に直に負担なく使えることがあります。施術の幅広く失敗なくアプローチしやすいということです。コツとすれば一時的に毛髪強度を上げたり色もちをよくさせるというトリートメント的に使う見極めの基準になります。
イメージは点滴の応急処置です。
今回の施術に使用した不活性リケラの理由は、クリープを使う施術であるので、ミクロクリープのSS/SH交換反応を司る活性に使うので、ゆっくり熟成させる必要性があったためです。ゆっくりとズレさせて髪の弾力性を確立させるために活性させる役割です。



的確で、理解しやすく良い回答だと思います。リケラを使用した場合、この解説が柱になると思うので、しっかり伝えたいですね。
今回の全てのパーマチュートリアルにおいてクリープ時に加温はされていないようですが、特に加温は必要ないとお考えですか?



はい。決して必要ないわけではありません。
健康毛やテストカールでカール率が足らない場合に稀に使うことはあります。
しかし現在ではあまりクリープで加温しません。
昔、圧縮蒸気がない時代とかシステアミンがまだ無いころは、湿熱加温をしていた時代がありましたが・・・・。
今回ではチュートリアムでのパーマ①~③施術がダメージ毛ということもありましたし、予め圧縮蒸気で加温できれば毛先まで伝えることができたこともあります。
大きな理由として、加温を活用した場合のクリープ促進は、アルカリ還元では中間水洗後に膨潤率が高いので移動の要素が強い。したがってカールがかかりすぎる要素が強く生まれやすく、テストカールより強くかかるからです。
タイムや1剤のパワーを調整して手前のテストカール判断が重要になると思います。



一般的にはまだまだ、クリープ=加温となってる場合が多いなと臨店講習などした時に感じることがよくあります。
私の場合、クリープの重要事項優先順位として ➀処理(CMC導入 骨格補整など)➁時間 ➂水分量 ➃温度(加温)と考えています。そして私の場合も➃温度までたどり着くことは滅多に無いです。
今回も二つの質問を通して行程パターンでの仕事では無く各行程での観察、見極めからの進行の重要性を示して頂けたと思います。
パーマチュートリアルお疲れ様でした。次に進みましょう。



ありがとうございました。
①処置
②時間
③水分
④温度
この優先順位、とても理解できます。
観察と見極め、また勉強になりました。
次回もよろしくお願いいたします。
課題:カラー①
■テーマ
ストカールっぽい質感を重ねたマット系カラーリング
■施術前の髪の状態
・前回かけたデジタルパーマがダレて毛羽が出ている。ダメージレベル3
・前回のアルカリカラーにムラ
・グレイは無し
■目指す仕上がり
・ダレたカールの再生
・ゲストの希望である赤みを消す大人のマット感
・ネジネジしないでセットができるデジタルカール
■施術前の髪の状態から考えた施術工程
①トイトイトーイシャンプー、タオルドライ
②前処理:シャンプーボールにお湯を貯めてBYACを溶かして毛先に付ける→全体に3種混合ミスト5倍塗布→チェンジリンス→特トリ→シブミンEX塗布→チェンジリンス
③薬剤塗布:リノベーターローション:ソニルクリープS:アクチベーター(5:5:2)を中間から毛先にスポイト塗布
④圧縮蒸気:全体に3分
⑤カラー剤塗布:中間~毛先部位にマットアッシュのHC/塩基性カラーを塗布。次に根元に1センチあけて塗布
⑥遠赤加温:20分
⑦お流し:お湯をためて指で拭うように乳化させる&トイトイトーイシャンプー
⑧後処理&前処理:へマヘマ10倍→シブミンEX10倍→毛先BYAC→へマヘマ10倍→チェンジリンス→リケラエマルジョン→ポリK10倍→毛先リケラミスト+リケラリノベーター(4:1)→チェンジリンス
⑨8割ドライ:ドライヤーで8割ほどドライする
⑩ストレートアイロン:うねりをとる程度(180度)
⑪毛先をワインド:デジタルロッドでワィンディング 80℃5分90℃5分70℃7分→クーリング
⑫2剤塗布:ロッドアウト後、3Dアンカークリーム塗布10分
⑬お流し
⑭後処理:へマヘマ10倍→ハイエマルジョン→キトキト10倍→チェンジリンス
⑮トイトイトーイトリートメント:流し
⑯仕上げ
■各施術工程の意図
②前処理:全体に3種混合ミスト5倍、BYAC原液
・カラーダメージ及びデジタルダメージ補修に親水から疎水に転換させる疎水型PPTの3種混合を利用して穴埋めをさせます。中間~毛先部位にはBYACを少しずつ付けることで、強度を確かめながら調整して導入していきます。
・シブミンEX:薬剤の使用感を最小限にしてキューティクルの疎水化
・特トリ:接着CMCを導入させて、スムーズなパーマ剤の通り路の確保
③薬剤塗布:還元させることで還元効果により、HC/塩基性カラーを入れやすくして定着させる。またストレートアイロンをかけることでうねりをとり毛先にカールを保持させる。
④圧縮蒸気:還元処理剤及びカラー剤の浸透促進のためスチームを当て毛髪のプレ膨潤の促進を行う。
⑤カラー剤:HC/塩基性カラー、ジアミン苦手のゲストの方にキューティクル付着のカラーを使う。また前還元することで染着性をアップさせる。
A:塩基性カラーの特徴として色持ちの良くないことが良くないというと言われるのは、分子量の小さいHC染料が抜け落ちるのが原因に上げられる。その中でどのようにして色を持たせるかを捉えた施術例である。
B:このストカールの還元処置をすることで、色が持つようにできるのが特徴である。その特化しているのが、寒色系である。寒色系というのは色持ちを良くすればするほど、次回の来店時に「くすむ」傾向がある。ならば、逆をとり低分子で色を入れられる寒色系は、残りづらいので浅く入れといてその還元作用により後々敢えて薄く残し「くすみ」を防げる特徴にある。
C:そのポイントは微還元であることです。あまり高アルカリで行うと、染まりは良いがダメージになりやすいし、Bで定義する色持ちが良くなることで寒色がくすみに繋がることにある。
D:この施術は、あくまで塩基性カラーをメインに捉えたものであり、ストレートもカールもその還元作用を利用して出来る施術として提案できる唯一のカラー施術と言える。
⑥遠赤加温:還元処理剤及びカラー剤の浸透促進
⑦乳化:カラー成分を均一に行き渡らせカラー定着を図る。
⑧へマヘマ:酸化重合を促進してカラー定着アップ
・シブミンEX キューティクルの疎水化と消臭
・BYAC:毛先内部構造の補強
・リケラエマルジョン:脂質補給とAEDSケラチン補給
・ポリK:緩んでる毛先引き締めてカラーの乗る土台を固める。
・リケラミスト+リケラリノベーター:ダメージ部位のケラチン不足にAEDSケラチンでSS結合のフォロー
⑫2剤アンカー:SSの再結合
⑭後処理:へマヘマ10倍→ハイエマルジョン→キトキト10倍、デトックス→内部補修→収斂・㏗調整
■修正を加えて施術
なし
■修正の理由
なし
■結果及び考察
大人のマット感表現は良い感じができたように思える。ただドライのみでカール表現可能かというとやはりセットのコツが必要になります。髪質感の向上においてはリトル商材の利点が出せました。







今回もよろしくお願いします。
さて今回カラー施術に塩基性カラーを使われていますが、私、塩基性カラーを今まで見たことも触ったこともありません。塩基性カラーについては全くのビギナーです。初めて塩基性カラーの講習を受けるつもりで臨ませていただきますので、塩基性カラーの特性、特徴、概要、勧めなどから教えていただけますか。
よろしくお願いします。



はい。わかりました。
最初は2~3年前に少し流行りはじめたのだと記憶しております。
塩基性カラーは、塩基性染料とHC染料が混合されているものがほとんどです。
分けて考えると説明がしやすいです。
概要として、塩基性染料は酸性基を持たない水溶性の染料で、マニキュアと同じでイオンで表面にくっ付き、カチオン性なのでダメージ部位に付着しやすいのでトリートメントと配合されて使われます。(塩基性カラートリートメント)
HC染料のほうは分子量が小さくて、キューティクルの隙間から入り込みビビットな色数が多いので色数が少ない塩基性と組み合わせて多くの色数を作っています。この二つの染料をミックスして作られているのが、HC/塩基性カラーです。
欠点は、塩基性カラーは色が良く抜け落ちると言われることで、化学反応が無い(分子が小さいままで電荷も無い)HC染料のほうが抜け落ちて色が持たないとよく言われます。
特性はジアミンフリーで、皮膚への影響はほぼありません。皮膚にも浸透しませんので経皮毒もありません。
特徴は表面吸着なので、キューティクルを開かないで染められます。染料そのもののために化学反応が必要無いので、髪と頭皮にとても優しいです。
勧めは、塩基性カラートリートメントです。
カラートリートメントの安全性としては断トツです。例えダメージ毛でもカチオン性のためによく染められます。そして色のバリエーションが豊富です。
臭いが全くありません。ノンジアミンのためアレルギーの人でも安心です。



大変解り易かったです。
還元させることで還元効果により、HC/塩基性カラーを入れやすくして定着させるとありましたが、還元させることで入りやすくなるのは何故でしょうか?



はい。還元することで、キューティクル間のSS結合を緩め、そこにHC/塩基性カラーが入り易い状態が作られるからだと思います。
特にエピキューティクルは疎水性の結晶ケラチンで水を弾きやすいですが、このS2を緩めることで親水効果に作用しやすくよりカラーが定着しやすいのではないかと予測しています。



今回は還元剤(還元行程)を利用してHC/塩基性カラーのポテンシャルを最大限にされているようですが、還元剤(還元行程)を使わない場合は浸促などで、毛髪を緩めることで、同じような効果が得られるでしょうか?
還元剤(還元行程)を使わない場合のお勧め処理などあれば併せてお答え頂けたらありがたいです。



はい。榊先生。
浸促などはその最もたるもので、カラー剤の浸透は必然的に良くなるしアルカリなので、HC/塩基性カラーの前処理としてベーシックにあると思うのですが、例えばダメージ毛やアルカリで弱い髪質ですと向かないかもしれません。
それならば、逆にBYACのほうが利用しやすいのではないかと感じます。
ダメージですと髪は-極に傾くので、一見カチオン性のHC/塩基性カラーは定着しやすく感じますが、ダメージし過ぎるとマイナスに偏りすぎてカチオンが付きづらい場合があります。このようなときはPPTが浸透しづらいのと同じで、HC/塩基性カラーも定着しづらいかと予測できます。
そのような時にグアニジルシスティンの強力なカチオン基が色の吸着を助けてくれるのではないかと思います。例えばブリーチ毛でダメージの髪にBYACで前処理、次に特トリでCMCを導入して色数豊富なビビットなHC/塩基性カラーで染めるなど面白いかと思います。



なるほど、浸促、BYACの使い分けですね。
リトル粧剤で適切な毛髪処理を施しておけば必然的にH/C塩基性カラーでの染まり、持ちは良くなると考えて良さそうでしょうか。



はい。本当にその通りです。今回も施術の中で埋もれてますが、リケラリノベーターのAEDSも実は塩基性カラーの染色を助けていると感じています。



その辺りもう少し詳しくお聞きかせ願えますか



はい。
やはりダメージしている毛髪は、システイン酸が生成されるというなかで塩基性染料とはイオン的には親和性は高められているかもしれませんが、効率的には吸着できてはいないと思うのです。
それは損傷レベルと大いに関係はありますが、均染色性や色もちというなかでどうしても抜け落ちやすいと思います。ところがAEDSが加わることで、効率的に毛髪強化することで染料の留まる力が高まり、染料の内部流出がしづらくなると感じています。



今回は大変勉強させていただきました。H/C塩基性カラーに興味が湧きました。早々に使ってみたいと思います。
カラー➀お疲れ様でした。次に進みましょう。



榊先生、ありがとうございました!
興味をもっていただいて光栄です。
また更に精進いたします。次回もよろしくお願いいたします。
課題:カラー②
■テーマ
パサつきやすいエイジングカラー毛にクリームバスリマサリで潤い感をもたらすカラーリング施術
■施術前の髪の状態
・新生部位15㎝白髪比率20%
・エイジング毛でのうねり
・毛先のパサつき
・軟毛でボリュームが出にくい。
■目指す仕上がり
・うねりを抑える
・7~8レベルのブラウン色
・パサつきを抑えてフンワリ感
■施術前の髪の状態から考えた施術工程
①前処理:3種混合原液+neoミスト5倍、ハイエマルジョン、特トリ、ポリK(100倍)塗布
②圧縮蒸気3分
③カラー塗布 アルカリカラー・ブラウン系(OX6%)新生部位→中間毛先に残液塗布15分放置
④中間処理:(シャンプー台)全体にヘマへマ(10倍)→ポリK(10倍)→キトキト(10倍)→乳化
⑤トイトイト―イシャンプー
⑥圧縮蒸気1分
⑦ワインディング
⑧クリームバスリマサリ:お湯=(1:1)をスポイトで塗布
⑨圧縮蒸気5分
⑩ロッドオフ
⑪後処理:へマヘマ(10倍)→パワードβ→キトキト(10倍)→チェンジリンス
⑫仕上げ
■各施術工程の意図
①3種+ミスト5倍:アルカリダメージ補修に親水から疎水に転換させるための疎水型PPT
ハイエマルジョン:接着CMCの補強
特トリ:接着CMCを導入させて、スムーズな剤の通り路の確保
ポリK100倍:緩んでる毛先引き締めてカラーの乗る土台を固める。締まりすぎないための100倍希釈
②圧縮蒸気
③カラー剤:ブラウン系アルカリカラー
④中間処理:ヘマへマ10倍→ポリK10倍→キトキト10倍→乳化
⑦ワインディング:
Aカラー前に圧縮蒸気を当て前処理
Bカラー剤後再度圧縮蒸気を当て、髪の内部に水分を入れて潤い感を促す。
Cアップステムでワインディング:テンションをかけることでストレッチ効果を生むと同時にボリューム感アップとうねり緩和。
D、 お湯とクリームバスを1:1で割ってかけて更に圧縮蒸気5分、ここでキューティクルを緩めクリームバスを浸透促進させます。ハチミツを多く配合されているクリームバスのハチミツの優しい香りを感じてもらい、また栄養補給をしながらつややかで潤い感のあるカラー毛に仕上げる。
⑪後処理:へマヘマ10倍→パワードβ→キトキト10倍→チェンジリンス
へマヘマ10倍:PPT同士の架橋up
パワードβ:等電点戻しと引き締め強化
キトキト10倍:等電点戻し
⑫ドライヤードライ
■修正を加えて施術
なし
■修正の理由
なし
■結果及び考察
カラーケアメニューとしての施術です。シンプルなカラー施術ですが、艶感とボリューム感がアップしました。ダメージ及びエイジングでハリを失いペタっとする髪にクリームバスリマサリを補給します。すると艶とハリを取り戻すストレッチ効果を生みます。















今回もよろしくお願いします。
先ず確認なのですが、前処理、中間処理、後処理で、通常のカラーダメージ回避は為されていると思います。
目指す仕上がりの項目で上げておられた、うねりを抑える、パサつきを抑えるというところは、主にクリームバスが担っていると考えてよろしいでしょうか。



はい。リマサリ成分と水分です。
施術はトリートメントかカラーどちらかで迷ったのですが、全体的ににカラー発色なども含めて良き効果が高まるのでカラーレポートにした次第であります。
アルカリカラーの欠点として、数種類のカラーリングのなかでも特に髪や頭皮へのダメージ度は高くなる傾向があります。その中で髪に水分とリマサリ成分が入ることで、うねりの緩和、アルカリでへたるボリューム感のアップ、パサつきを抑えてカラーの艶み感をアップがポイントになります。
リマサリのハチミツには保湿剤のグリセリン同様の保湿作用があります。これを利用してダメージやエイジングで痩せた髪や硬くなった髪に、水分補給をして弾力をもたらしカラーの発色を促していきます。
また頭皮にもスキャルプアプローチをかけてヘッドスパ同等の頭皮環境の整えにも促していきました。



エイジング、うねり、パサつきときたら、リケラ(リノ、アクチ)を施術に組み込みたくなるところですが、クリームバスチョイスなのは、頭皮ケアを重要視しての事でしょうか。
加えて、ワインディング行程でボリュームアップを図られていると思うのですが、それもクリームバスチョイスに関係していますか。



はい。頭皮ケアは大きいです。
クリームバスはそもそも頭皮マッサージに使用するものですから、特に頭皮トラブルがある場合、頭皮や髪に栄養成分が入り込む役割です。
ワインディングにおいては、テンションを加えることです。
テンションを加えることで毛髪ストレッチに繋がります。キューティクルが水分により開閉する状態で、CMCに水分を補給するイメージです。
カラー施術では㏗によりキューティクルの剥離とCMCの溶解・流出となりやすいので、リマサリが酸性のためアルカリが消滅していくイメージをしています。
ボリュームアップではむしろ水分のほうのが重要ではないかと思います。



ポイントを押さえた回答ありがとうございます。
クリームバスのスペックを十分に生かしたカラーケアであることが伝わりました。
次に進みましょう。



ありがとうございます。
次回もどうぞよろしくお願いいたします。
課題:カラー③
■テーマ
ハイライトを活かした毛髪強化トーンダウンカラー
■施術前の髪の状態
・ハイライトダメージ
・セルフアイロンのため毛先の髪密度の薄さ
・まとまりが悪い
■目指す仕上がり
・落ち着いた大人のカラー
・毛先までの柔軟なしなやかな質感作り
■施術前の髪の状態から考えた施術工程
①シャンプー
②ダメージ部位にBYAC原液塗布→チェンジリンス
③前処理:3種混合原液+neoミスト(5倍)→ハイエマルジョン(しっかりするまで2~3回)→ダメージ部位に特トリ→ポリK(100倍)
④カラー剤塗布:根元に7トーン→10分放置→中間毛先に8トーン塗布→10分放置
⑤中間処理①:セット面-へマヘマ10倍、ポリK10倍、キトキト10倍
⑥乳化
⑦トイトイトーイシャンプー
⑧後処理:へマヘマ10倍→パワードβ→キトキト10倍→チェンジリンス
⑨トイトイトーイトリートメント
⑩仕上げ:ボリュームアップミスト→リケラミスト
■各施術工程の意図
②BYAC-毛先内部構造強化
③前処理:
3種ネオミスト5倍-ダメージ補修に親水から疎水に転換させる疎水型PPT
ハイエマルジョン-緩んでいる毛先の引き締めとカラー剤の発色促進補強(髪質的にはパワードエマルジョンですが、㏗の過収斂も吟味してハイエマルジョン使用)
特トリ-接着CMCを導入させて、カラー剤の定着効果
ポリK100倍-ダメージ部位の収斂(100倍使用は過収斂を防ぐため)と疎水効果
⑤中間処理①:
へマヘマ10倍-酸化重合の促進
ポリK-ダメージ部位の収斂して染料定着させる
キトキト10倍-pH戻し
⑥乳化:浸透圧により染料を髪に均一に行き渡らせてカラー剤発色定着
⑧後処理:
へマヘマ10倍-過酸化水素の除去
パワードβ-等電点戻し、毛髪内部引き締め
キトキト10倍-pH調整、外部補修
■修正を加えた施術箇所
なし
■修正理由
なし
■結果及び考察
毛髪強化においては申し分なし。さすがリトル商材の威力です。カラーにおいては明度が狙いよりダウンでした。















今回もよろしくお願いします。
今回の施術で、このチュートリアルを見ている方、もしくはこの施術の講習を受講された方に伝えたい事はどういったことになりますか。



今回もよろしくお願いいたします。
目指したのは落ちつき感のあるカラー発色と毛先までのしなやかな質感作りです。
ハイライトダメージによる体力を失われた毛髪に、いかにして着色してしなやかな髪作りを施していくかですが、まずこのブリーチダメージ(ハイライト)によりシスチン含量の低下とシステイン酸含量の増加が出ます。特にシスチンはシステイン酸へ酸化してタンパク質自体が分解し、シャンプーにより毛髪から溶出されます。「しなやかさ」は毛髪の水分量が失われると減少してしまうので、ダメージ対策として外部からケラチン類で補強することに意義が必要になります。
まずキューティクルの失われた量ですが、ブリーチをすると外層部分のシスチン量の減少は高く架橋構造のジスルフィド結合は開裂してCMCとタンパク質は流出することでボイド(大きな空洞)ができます。このボイドを隙間なく埋めるために疎水グラフトPPTが必要で、3種混合neoミストが重き必要になります。
これでボイドが埋まり髪の11%~14%の水分量を保持させて疎水に転換させていくことです。
これを保持させるためにポリフェノール(ハイエマルジョン)で引き締めを行います。
またダメージでCMC類の抜け落ち液晶ラメラ構造が壊れてますので、キューティクルの剥がれ補修に特トリで接着CMCの導入も行います。
この土台作りをしっかりやった上で、目指す落ち着いた大人のカラー作りが可能になります。
カラー剤の発色と色持ちの増強作りです。
もう一つにまとまり感の為のしなやかさですが、これは髪をニュートラルに戻す意味で等電点にする意味を生じます。これにはヘマへマ・ポリK・キトキトです。中間時の過水除去にへマヘマ、ポリフェノールで余分な水分を押し出して髪を引き締め収斂させるポリK、そしてpH調整に等電点(4,5~5.5)戻しにキトキトです。+と-を打ち消す0の状態を作る役割です。
また後処理でもデトックス、収斂、㏗調整をします。
デトックスにへマヘマを使いルイボス効果を担います。パワードβで収斂効果及び等電点戻し。キトキト㏗調整をします。
これらのことによりカラー施術前の髪に状態(ニュートラル時)にすることで、しっかりとしたヘアカラー発色と大人カラーの色持ちが可能になります。



質問の答えとしては、土台をしっかり作ってのカラー施術、そしてニュートラルな状態に戻してフィニッシュということですね。
細かく質問させて頂こうと思った部分も盛り込んで頂いて重ねてありがとうございます。
②、③にダメージ部位とありますが、これは施術前の状態にあった髪密度の薄い部分と考えてよいでしょうか。



はい。そうです。
毛先と特にハイライト部位の部分です。
この部位はなんとか結晶構造を維持している状態でした。



「この部位はなんとか結晶構造を維持している状態でした」ということですが、結晶構造が維持できていないと判断した場合、処理は変わりますか。結晶構造というものも併せて説明頂けるとありがたいです。



はい。
結晶構造とは、分子が規則的に配列した構造状態のことで、毛髪ですとケラチンコルテックスのミクロフィブリルタンパク質とマトリックスタンパク質の網目構造を指します。
ケラチンのSS架橋の数、様式など規則的に配列されてる状態が崩れますと、毛髪の弾性が著しく失われます。色素メラニンはコルテックスにありますので、ブリーチダメージによりメラニンは溶出され、また日々の高熱アイロンにより繊維構造が変性しやすくなります。艶が低下してパサついた状態になります。来店時は、シャンプーシリコンによって構造はなんとか支えられていた状態でした。
維持できていない状態ですと、ミクロフィブリルまで分解され断毛やビビリ毛に変化してしまう危険性も出てきてしまうので、そうなる前にリトルの疎水処置を行うのが良き判断になります。



「そうなる前にリトルの疎水処置を行うのが良き判断になります。」まさにその通りですね。
明度が狙いよりダウンということですが、これは今回の処理のどこかが影響しているのでしょうか。



はい。
カラー塗布前の前処理ですが、
「③前処理:3種混合原液+neoミスト(5倍)→ハイエマルジョン(しっかりするまで2~3回)→ダメージ部位に特トリ→ポリK(100倍)」
3種・特トリのダメージホールの穴埋め・接着をエマルジョンで2~3回行ったのですが、収斂することで出口が狭められてPPTの流出をおさえることができたのですが、逆に収斂させすぎてアルカリが働きづらいのかと予測しました。詰めの甘さを感じました。
このようなときの施術例として、榊先生の施術ケースレシピをお聞きしたいのです。
参考になることがあれば、ご教授お願いいたします。



そうですね。収斂し過ぎているとなると発色が表面に集中してトーンダウンしてしまうことも考えられますね。
私の施術もほぼ、渡邊さんと同じ施術になると思います。唯一違うとすれば、⑤の中間処理のヘマヘマの濃度ですかね。
私の場合、中間処理のヘマヘマは30倍〜100倍くらいを使います。
後処理時には過水をしっかり分解したいので、10倍がマストにしています。この時もの酸化重合の促進もあると考えているので、中間処理のヘマヘマの濃度は抑えめで行なっています。
ご教授と言う程ではないので、意見交換的に如何でしょうか。



はい。酸化重合の促進ですね。内部収斂と染料の定着UPの使い分けを深く捉えて施術します。アドバイス感謝いたします。ありがとうございます



それでは、次に進みましょう。
カラーチュートリアルお疲れ様でした。



はい。ありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします。
課題:トリートメント①
■テーマ
ダブルヘアストレッチ・トリートメント
■施術前の髪の状態
・うねりと細毛のミックス
・カラーダメ―ジ(他店施術)
・中間から毛先はセルフアイロンのダメージ
■目指す仕上がり
・しなやかでドライだけでシュッと仕上がる
・艶感とハリ感の向上
■施術前の髪の状態から考えた施術工程
①トイトイトーイシャンプー
②浸透促進原液+neoミスト(5倍)→タオルドライ
③ツインブラシによる完全脱水ドライ→1stストレッチアイロン180℃
④前処理:全体に3種混合原液+neoミスト(5倍)→毛先に3種混合原液(原液)→全体にリケラエマルジョン→ポリK(5倍)→チェンジリンス→毛先にBYAC(原液)→シブミンEX(5倍)→チェンジリンス
⑤ハンドブローによる8割ドライ→2ndストレッチアイロン180℃
⑥ソニルCA-H塗布(3分放置)→シブミンEX(5倍)→トイトイトーイシャンプー→へマヘマ(10倍)→キトキト(10倍)→チェンジリンス
⑦質感調整:いきいき(5倍)+リノベーターローション+リケラミスト(1:1:4)→圧縮蒸気3分
⑧2剤:BⅡローション揉み込み塗布3分+3分→へマヘマ(10倍)→キトキト(10倍)→チェンジリンス
⑨トイトイトイ―イトリートメント→お流し
⑩仕上げ:アウトバス:アジアンムーン少量→ドライヤードライ
■各施術工程の意図
②浸透促進(5倍)毛髪内のタンパク質を緩めアイロン施術による歪みを均等にする。浸透促進剤を最初に入れておくことで毛髪内部の固定の結合が緩み、歪みの部分が変化しやすくなる。
③完全脱水ドライ:ストレートにすることと水分を残さないことでアイロンダメージ回避
1stストレッチ:うねりを取り真っすぐに固定する目的。
④.前処理:3種混合+neoミストと3種混合原液 PPT補給と疎水化→リケラエマルジョン(脂質補給とAEDSケラチン補給)ポリK髪の引き締め→BYACダメージ補修のための疎水転換→シブミンEX キューティクルの疎水化と消臭
⑤8割ドライ:水分を残すことで毛羽立ちの防止。
⑤2ndストレッチ:ゆっくりと水抜きによるしなやかさの質感調整保持
⑥ソニルCA-H:手触り感を高めるためにハードな還元剤→へマヘマ10倍:PPT同士の架橋up→キトキト10倍:等電点戻し
⑦いきいき+リノベーター+リケラミスト:高低双方のケラチンで髪の強さとハリコシのフォローとダメージ部位のケラチン不足にAEDSケラチンでSS結合のフォロー
⑧BⅡ:ケラチンの再結合
⑩アジアンムーン:しっとり仕上げ補給
■修正を加えた施術箇所
なし
■修正の理由
なし
■結果及び考察
これは矯正ではなくトリートメント施術と踏まえた納得の施術でした。質感の課題である艶感としなやかさは十分でした。穴埋め 接着 収斂というなに一つかけても不十分になってしまうトリートメント施術の奥深さを実感しました。















今回もよろしくお願いします。
この施術では、アイロン行程が2回ありますが、その狙いと効果、作用などについてもう少し詳しく解説願えますか。
またアイロン行程1回の場合との違いについてもお願いします。



はい。よろしくお願いいたします。
リトル推奨の「ヘアストレッチ」にもうひと手間かけて行う、2回に分けたアイロン施術によるストレッチ施術「ダブルヘアストレッチ」です。
1回目に浸透促進剤に含まれる尿素の働きとアミノ酸界面活性剤の力で、より水分量を増やし熱により髪の歪みを修正します。そして薬剤の浸透性も向上させます。
目的は、うねりの癖を取り真っすぐに固定するのが目的です。
うねりの癖、そして根元の新生部位の癖は、毛髪内部の結合が安定し固定状態です。
この固定状態を浸促を使い柔らかくして、うねりをより少しでも伸ばしておくことです。
ポイントは完全乾燥させた状態でのストレッチです。
完全乾燥状態で真っすぐに固定された癖は、一時的に固定されます。
次は固定された状態で疎水処理を行います。それにより求める形で疎水状態により固定されます。
そのときにAEDSも使用してSS量を増やしビルドアップもさせます。
2回目のストレッチは8割ドライの水抜きストレッチを行います。水分をゆっくり抜き毛羽も防止します。そして毛髪の軟らかさを作ります。髪本来の体力を温存してカラーやパーマをする下地作りを作ることができます。
最後にCAで優しく還元して、癖とうねりを緩めてフォローさせます。
ヘアストレッチは、ストレッチさせた状態で還元剤を効かせ、毛髪をアイロンで作った形に均すこと。
ダブルストレッチは、ファーストストレッチさせた疎水状態を固定し、セカンドストレッチで毛髪の求める質感作りを保持させるための容形成です。



追加の質問になるのですが、このモデルさんを通常のヘアストレッチで施術したとすると今回のダブルストレッチ施術の結果とどんな違いが出ると考えられますか。



はい。
通常のヘアストレッチをしてた場合では、まずこのモデルさんの場合癒着を起こしていたので、通常ではうねりが取れづらいという予測が付きます。セルフによるアイロン施術は高熱で歪み乾燥収縮してましたので髪が過剰の膨潤をしています。1stで浸促で浸透させ柔くさせる作用を起こします。そのあとで、CMCとポリフェノールを入れ込み疎水固定を促し2stアイロンへ進ませます。
この癒着毛に対してのアプローチ施術の方法として通常のヘアストレッチでは、毛髪のしなやかさ作りの面で物足りないかなという感じを予測しました。



はい。しっかり理論化されていますね。回答ありがとうございます。
このダブルストレッチはどのような方が対象のメニューと考えればよろしいでしょうか。



はい。
タンパク質変性をしている髪が対象になります。
タンパク変性の癒着毛は水が入りづらい状態、まして内部コルテックス内は吸水ムラが生じています。
当然にトリートメント剤も浸透しづらいので、浸促により毛髪内部の水分量を増やし、柔くして吸水ムラを防いだあとにまず完全脱水のストレート固定をかけます。それによりうねりを取り、そのあとはリトル推奨のヘアストレッチトリートメントの工程に続いていきます。



では、還元剤について質問させていただきます。
⑥で「ソニルCA-H:手触り感を高めるためにハードな還元剤」とありましたが、これについて解説お願いできますか。



はい。わかりました。
まずシステアミンはある程度強めの薬剤を使用したほうが手触り感は良くなります。
チュートリアルレポートNO4のパーマ①でも言いましたが、強い還元剤ほど還元時間が短いので、短時間で抜き取り、パーマ剤は内部残留しないので毛髪のダメ―ジロスに繋がります。ダメージロスほど手触りは良くなります。
またシステアミンの特色でもありますが、+に帯電していてアルカリをたくさん与え㏗が高くなると疎水性が高くなり+電荷がうちけされて浸透します。弱めほど浅い位置の還元になりしかも長い還元になりダメージしやすいという理由です。特に低㏗は+電荷が強いためカチオンで感作性が高くなり皮膚にも残留しやすくなります。



ハードな還元剤を使うのは臆する人も多いと思いますが、その作用、特性をしっかり理解しておけば、ダメージロスの武器になるということが伝わる回答だと思います。
今回の施術は全体を通して、薬剤の理解とそれを生かす施術がいかに大事かを考えさせて頂けるお手本のような施術だったと思います。
正に「穴埋め 接着 収斂」何ひとつ欠けても‥‥ というのを見せて頂けました。
各回答にも勉強させて頂きました。
ありがとうございました。次に進みましょう。



ありがとうございました。
これからのトリートメント施術にたいしても、「穴埋め、接着、収斂」そして「脂質導入」これらも肝に銘じながら施術していきます。
次回もまたよろしくお願いいたします。
課題:トリートメント②
■テーマ
骨格強化還元トリートメント
■施術前の状態
セルフアイロンでのダメージ
根元も含む柔いうねり
ごわつき
熱変性多少と内部流出
■目指す仕上がり
スリークな仕上がり
しなやかさとまとまり感
■施術前の状態から考えた施術工程
①リノベーターの活性化 リノベータークリーム:アクチベーター(19:1)10分
②トイトイトーイシャンプー
③毛先newBYAC
④全体に3種混合原液+neoミスト(5倍)→特トリ+リケラエマルジョン(1:4)→ポリK(10倍)→チェンジリンス→タオルドライ
⑤根元から毛先まで、ソニルチオ:ソニルチオH(1:1)を塗布 1分還元
⑥毛先のみ水洗(根元はそのまま)→タオルドライ(根元はそのまま)
⑦毛先に活性化したリノベータークリーム:アクチベータ(19:1)塗布
⑧10分放置(根元はトータル20分放置したことになる)
⑨全体お流し→シブミンEX(5倍)→ヘマヘマ(10倍)→キトキト(10倍)→チェンジリンス
⑩ドライ→アイロン180℃
⑪全体にアンカー(10分)→お流し
⑫ヘマへマ(10倍)→パワードβ→キトキト(10倍)→チェンジリンス→トイトイトーイトリートメント
⑬リケラミスト→仕上げブロー
■各施術工程の意図
①リノベーターの活性化:アクチベーターでリノベーターのAEDSのSS結合を切る
③疎水処理:ダメージでマイナス電荷の部位にSS結合を導入させる
④前処理:ダメージ補修に親水から疎水に転換させる疎水型PPTの3種混合+特トリを利用して穴埋めと接着をさせる。さらにしっとり感をもたらすようにエマルジョンCMC骨格を整えた。ポリK:ダメージによる吸水した髪の引き締め
⑤軽くうねりをとるためにソニル:ソニル(H)1:1アルカリ度3.6で還元させる(根元~毛先まで)
⑦リノベーター:アクチベータ(19:1):ソニルチオによりSS結合が開いているところに活性化したAEDSを浸透させて骨格を強化させる。
⑨シブミンEX:消臭と乳化破壊。 へマヘマ10倍:PPT同士の架橋up。
⑫パワードβ:引き締め。 キトキト10倍:等電点戻し
⑬リケラミスト:ポリアミンAEEによる熱ダメージ防止
■修正を加えた箇所
なし
■修正理由
なし
■結果と考察
手触り感、しっかり感及びまとまり向上。癖も落ち着きました。ただ、毛先をもう少し疎水化をかければ良かったのか?毛先の収まり感は課題です。















今回もよろしくお願いします。
先ず確認でお聞きしたいのですが、⑥⑦で毛先、根元という表記がありますが、それぞれ具体的にはどれくらいの範囲を示しますか。



おはようございます。今回もどうぞよろしくお願い致します。
根元は画像でお見せしているとおりの、新生部位(黒いうねり部位)8㎝。
毛先は、毛先は毛羽のでている部位の約6㎝。
中間はグラデーション塗布でそのまま残しました。



では、結果と考察のところから触れていきたいと思います。
考察通り毛先にもう少し疎水化をかけるならどのような処理、施術を組み込みますか。



はい。疎水化が足らないと思ったのは、「しなやかさ」が足らないと持ったからです。
トリートメント施術で常に思っていることは、根元と毛先は同じ質感でしなやかさをもたらせたいといつも思っています。今回ハリコシが足らなく親水域に偏りを感じました。
「④全体に3種混合原液+neoミスト(5倍)→特トリ+リケラエマルジョン(1:4)→ポリK(10倍)→チェンジリンス→タオルドライ」
脂質に関しては特トリ+エマルジョンで良かったと思うのですが、ポリKの10倍は収斂が締めすぎたかなと感じています。やはり脂質で接着したあとの不容易な収斂で、あとの脱水ブローの水抜けが悪く親水性を保つままアイロン固定になってしまったのか?と予測しています。
ポリフェノールの濃度、量、回数をもう少し繊細に感じとり施術枠を広げていけねばいけないと感じました。ポリの10倍は基本ですが、~20倍から50倍までを考え手の感覚で感じ取り施術がベターと思います。「穴埋め・接着・収斂」の見直しです。



しっかりとした考察ありがとうございます。私もポリkは大体20倍から使用することが多いです。
今回、毛先の収まりに言及されていることを受けて、私だったら⑥と⑦の間にキトキト処理を入れると思うのですが如何でしょうか。
たとえ1分でもアルカリ膨潤方向に向いている状態を等電点に近づけてからのリケラ導入という感じです。



はい。おっしゃる通りだと思います。
サロンワークでは、2剤にOXも併用することも多くので、つい炭酸泉に頼ってしまいます。
やはりこの場合キトキトも10倍希釈で妥当でしょうか?



そうでね、この場合先ず10倍希釈が妥当と考えます。それでも膨潤を感じるようであればチェンジリンスなり濃度の濃い物の再導入なりで対処すると思います。
今回の施術、縮毛矯正施術の中でSS解放時を利用して毛先6㎝に骨格強化還元トリートメントを施す施術と理解しております。経験の浅い方がこの施術を実践しようと思った場合、1度還元剤の入ったところにさらに還元剤を入れる事に躊躇される方もいらっしゃるのではないかと考えるのですが、その辺りはどう説明されますか。



はい。リケラの骨格強化は、活性化されたケラチンを髪内部に導入して、髪のケラチンとSS結合で繋げて髪の一部に変化させていくのが骨格矯正です。
しかし長所は短所へもなり得ます。
この場合熱変性された髪であり、それでなお加齢にて水を吸って膨潤しやすい髪は、軟化の膨潤度の差でケラチンが吸われやすくなっています。リノベータとアクチベータ(今回は19:1)を基本通りに使用すると硬い仕上がりを見せやすい場合があります。ポリKや特トリを使いすぎた状態とよく似ていますね。そのような場合はリノベータの量で調整しますが、この割合が判りづらいのです。
よく髪を家に例えて、地震に強く補強させるために柱を足しますが、欲張って柱を入れ過ぎて丈夫過ぎる家になり返ってバランスの悪い建築物になると言われています。髪に例えると撥水毛みたいな髪ですね。
であるなら、最初に増やす分の柱を前もって取っておけば、バランスを取れやすい状態をつくることが出来ます。前還元で一瞬SSを切っておき(例えるなら強い柱を抜いておき)そこに活性化させたケラチンを導入させれば、基本通りの割合のリノベータとアクチベータでも硬くなり得ず、わかりやすく骨格矯正できるようになります。



前還元がリケラの長所を活かす前処理に成り得るということですね。
もし、今回の施術で、1剤(TIO)を流した後、ミックスしたてのリノベーター:アクチベータを塗布していたら仕上がりはどう違っていたとお考えになりますか。



はい。ケラチンを活性化させないでのリノベータ+アクチベータというこですと、この場合は4%濃度のGMT還元剤としての仕様になります。
SS量の調整としてでなくパーマ剤として使うので、チオで1st還元→GMTの2st還元のダブル還元です。トリートメント施術という髪質強化というので無く、ストレートパーマ施術ということになります。
癖は伸びますが単なる質感調整という表現で、毛先の収まりをみせる装いになると予測されます。



活性リケラを使うトリートメント施術の場合、不活性リケラについても触れとくとトークポイントになって解りやすいと思います。
それでは、次に進みましょう。



はい。アドバイスありがとうございます。
活性化リケラのみならず不活性化仕様についても、触れておいてのリケラ骨格強化施術ですね。
理解いたしました。
またよろしくお願いいたします。
課題:トリートメント③
■テーマ
毛髪ガラス化転移トリートメント
■施術前の髪の状態
・5か月前に他店ヘアカラー、これからはカラーを止めて黒髪に戻していく予定
・うねりと膨らみを抑えるため日々セルフでのアイロン
・毛先に熱変性
■目指す仕上がり
・しなやかさとスリークなストレート艶髪
■施術前の髪から考えた施術工程
①トイトイトーイシャンプー
②毛先にBYAC(原液)
③中間~毛先にパワードベータ(原液)
④シブミンEX(5倍)~チェンジリンス
⑤3種混合原液+neoミスト(5倍)
⑥ハイエマルジョン(原液)
⑦特トリ
⑧セット面で超音波アイロン
⑨中間~毛先にパワードベータ(原液)
⑩シブミンEX(5倍)フォ―マーでひと手間
⑪100℃アイロン
⑫クーリング3分
⑬水洗
⑭ポリK(20倍)
⑮へマヘマ(20倍)
⑯キトキト(20倍)
⑰タオルドライ~アジアンムーン
⑱ドライヤー8割ドライ
⑲180℃アイロン(1パネル2~3㎝)
■各施術工程の意図
②熱変性部位のダメージ強化と補修 *手ごたえを強度を回復させるため何度か行う。ただし硬くさせ過ぎないように注意。
③脂質補給、親水毛への転換 *中身詰めの意識を持つ。 路づくり→脂質補給→接着への準備
④消臭
⑤ケラチンPPTの補給、穴埋め→路づくり
⑥脂質導入 タッピングによる数回の繰り返しの導入です。
⑦接着 同じく内部に浸透させます。
⑧振動による補給定着 ケラチン穴埋めと仮止め 2スルーさせます。
⑨脂質導入 タッピングにより導入。手ごたえがあるまで何度か行う。
⑩グルコン酸亜鉛によるタンパクと脂質の結合
⑪CMCのガラス転移 2~3回のスルーです。
⑫CMCを固める 冷やしの目的
⑭手ごたえを感じながら硬くなり過ぎないように収斂させました。
⑮PPTの定着
⑯㏗調整、等電点戻し
⑰18MEAの補給 毛先中心塗布
⑱圧縮蒸気を髪内部に発生させて転移温度を下げる。デンマンブラシでドライです。
⑲ケラチンのガラス転移化、艶感を出していきました。
■修正を加えた所
なし
■結果及び考察
シンプルな転移トリートメントを丁寧に施術しました。
シンプルほど難しいですが効果測定がしやすく、路作り→穴埋め→接着→収斂→外部補強を基本構造として
途中途中繰り返す中で大きな気づきがありました。溶剤の濃度の重要性を手で感じ取ることで、最後の質感が変わり転移が完成することを感じとることができたのが大きいのです。
転移トリートメントは最後にアイロンワークで完結しますが、その前に既に毛髪内では完結しています。
見た目より内部を感じ取れる施術だと感じることが大切です。















今回もよろしくお願いします。
目指す仕上がりにストレート艶髪とありますが、ガラス転移トリートメントで目指すストレート艶髪とはどういう物かもう少し詳しく説明頂けますか。



はい。
髪のダメージというのは、痛みをはじめ、枝毛・切れ毛・パサつき、そして乾燥など様々です。
それらのダメージ改善、そして癖であるうねり・捻れ・ごわつき・アホ毛などや髪の広がり、ザラザラの手触り感など質感の改善、またヘアカラーの色持ち、パーマの持ちなどのデザイン維持力の改善。
それらを修復していくのがトリートメントの目的であります。
本来の髪質や癖などの影響もありますが、それよりも間違ったヘアケアによりダメージさせている場合もあります。これらを良くするために改善させていくことで、髪本来の自然なストレートの艶髪が生まれます。ガラス化することで、外壁が綺麗になるだけではなく本来の元気さを取り戻すことで、安定してパーマやカラーの持ちが良くなり傷みにくくなるという効果があげることができます。
安定差の相違はまず持続力が上げられます。髪の2つのガラス転移点・CMC転移、ケラチン転移を活かすことで、枝毛・切れ毛の修復これらは内部補修、そして外部補修にアイロンの圧縮蒸気で転移温度を下げてケラチンを転移して艶感を継続できることそして、自然なストレート艶髪を維持できる要因であることが、ガラス化転移トリートメントで目指していく艶髪であると感じます。



申し訳ないですが、質問を追加します。
モデルさんのビフォー写真 では、うねりが確認できます。
目指す仕上がりがストレート艶髪ということはガラス転移トリートメントでうねりを伸ばしストレートにするという理解でよろしいでしょうか。



はい。
3種混合ミストには、アミジノシステイニルΦ型ケラチンには分子内に強いカチオン基とSH基が多数入っています。仮止め時点でSS/SH交換反応を毛髪内で起こして、アミジノステイニルΦ型ケラチンの一部のSH基を髪の中にSS結合を介して定着させています。この仮止めによりアミジノステイニルΦ型ケラチンの残りのSH基は日数を介してSS/SH交換反応を起こしてSS結合が強化されていきます。
ストレート形状にしたことで、日常のヘアケアも相成りつつSS結合の強化をも伴い、うねりも少しづづ収まりを見せることになります。「うねりを伸ばしてストレートにする」は少し語弊があるかもしれません。縮毛矯正施術ではないので。「うねりを落ち着かせて艶髪ストレートに見せていく」くらいで良いかなと思われます。
先日ゲストに一週間後(施術日・7/18/土)の様子をメールでお尋ねさせていただきました。かなりうねりと捻れによる膨らみも収まりスリークを保っているということでした。



そうですね。「目指す仕上がり」はこの施術の着地点になると思うのでチュートリアルを見ている方、もしくはこの施術を講習で受講される方などにガラス転移トリートメントでストレートになると勘違いされないように気をつけなくてはいけないですね。
⑧についてお伺いします。超音波アイロンが無い場合、補給定着はどのように行えばよいでしょうか。
またリトルのマニュアルではツインブラシブローの部分だと思うのですが、超音波アイロンを使う利点なども教えてください。



はい。超音波アイロンが無い場合は、補給定着はマニュアル通りのツインブラシでブローで十分かと思います。
超音波アイロンの利点は、1MHzの超音波振動により熱及びアルカリを使わずにキューティクルを開かさないで、薬剤を髪内部まで浸透させることです。
水滴をマイクロミストにして、また3種、特トリなど処理剤のクラスターをナノ化して髪のコルテックスを振動させて髪内部まで浸透させます。熱もアルカリも不要なので膨潤もなく極力ダメージレスで時間短縮になります。



より効果の高い手段を見つけるのがトリートメント追求の醍醐味ですね。
⑰のところですが、リトルマニュアルではリケラエマルジョンも使用するようになってますが、エマルジョンを外したのは何か理由がありますか。



実はこのゲスト様、どうやら以前よりリトルの商材を使っていただいてるらしいのですが、リケラエマルジョンの香りは苦手だそうで、その前はベーターレイヤーエマルジョンを使っていたらしくこちらは気に入って使っていたみたいですね。香りに関しては女性特有の拘りがあるもので、私はどのような状況でも香りを確認していただき購入して頂くようにしております。というわけで今回使用を外しました。そのためのアジアンムーンに役割をはたして頂きフォローしております。



なるほど、そういうことなんですね。180度アイロンに向けてポリアミンAEEは入れ時たかったですね。香りの問題は難しいですね。
それでは、最後に、このチュートリアルを見ている方、これからガラス転移トリートメントを取り入れていこうと思っている方、さらに追求してより良い結果を出したいというような方に向けてアドバイスをお願いします。
ガラス転移トリートメントのコツだったり、薦めだったり、失敗例だったりなんでもかまいません。よろしくお願いします。



はい。わかりました。
ガラス化転移トリートメントは2つのガラス転移点を利用した持続力の強いトリートメントですが、
基礎になっているのは、疎水トリートメントです。
疎水にすること、疎水に近づけること、そのために「毛髪診断」を正しく行える必要性があります。
「毛髪診断」を的確にできれば、トリートメントのみならずパーマやカラー、ストレートもお客様の要望にも応えることがしやすいと感じます。
疎水に戻すためのベーストリートメントの設計ですが、
①路づくり・・ナノ化CMC
②穴埋め・・疎水グラフトPPT類
③接着・・脂質類の補給
④収斂・・ポリフェール
⑤外部補修・・キューティクル補修
この②から④が最重要であると感じます。
疎水にするための強度回復を数回繰り返す中で、処理剤の濃度の使い分けをすることで効果が出る瞬間を手で感じ取れるまで重ねていくことがコツです。わからないときはわかるまで繰り返して覚えることです。
疎水化=健康毛が成り立つとすれば、「しなやかさ」の確保が重要です。強度回復が感じ取れればしなやかさは確保できるはずなので、中身を詰めていき手で感じ取れた瞬間(わかるはずです)に収斂させていきます。このチェンジリンス工程で有効成分だけ残せるように、お湯を加えながら浸透を促して他の成分は流れていくイメージです。イメージを持つことが重要で、髪創りもイメージを描いていけばそこに近づいていくはずです。
ガラス化転移は、水分と温度のバランスが重要と考えます。
ケラチンの補給定着(仮止め)にツインブラシでブローですが、アミノジシステイニルケラチン吸着upのためここで乾かしすぎないようにします。脱水と蒸すことでSS/SH交換反応が進む要因になります。ガラス化の重要ポイントのCMCガラス化転移ですが、接着のあとの100℃アイロンでCMC 残存力upにつなげていきます。溶かし入れるときにアイロンスルーするのですが、私は以前ここでスルーをプレスしてしまいダメージに繋げるという失態をしたことがありました。ここではあくまでアイロンスルーに徹することです。
最後にケラチンのガラス化に80%ドライの180℃アイロンで圧縮蒸気を髪内部に発生させて転移温度を下げて、毛髪外殻の造形作りを行いフィ二ッシュさせます。
ガラス化転移トリートメントは、シンプルですが奥深いトリートメント技法です。それだけに持続力の強い高級トリートメントで、物にすればサロンの大きな武器に必ず成り得ます。



私も臨店、講習等で「見て」「触って」毛髪の状態を感じとる事が丁寧なトリートメントだと思う、だから日頃の処理からその感覚を磨きましょうと伝えております。ガラス転移トリートメントは まさにその集大成だと思っております。
それではチュートリアルを終了致しましょう。たくさんの課題大変お疲れ様でした。



榊先生、12回のチュートリアルをご指導いただきありがとうございました。
長いようで、短くもあり私にとって充実した期間になりました。
この年になっても学ぶことは永遠に終わることが無い美容人生です。
その中で数々の「師匠」と出会えましたが、また新たに出会えたことにとても感謝しております。
チュートリアルすることで、知識を深めくきわめること、また美容業の仕事の深さそして進化の著しい業界への自信につながる一歩になるものと感じています。
お会いできることを楽しみにしております。